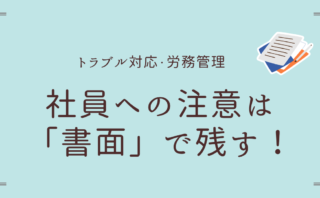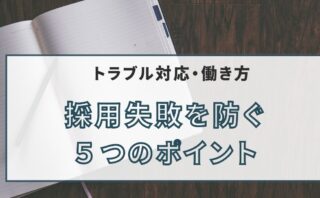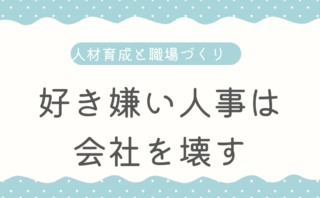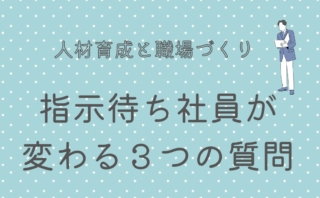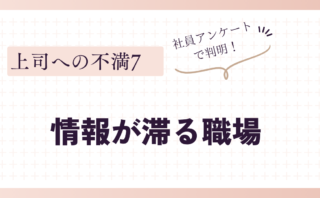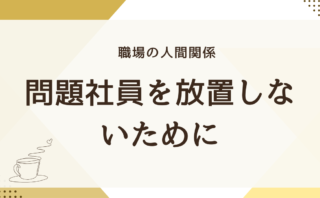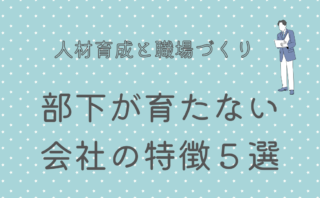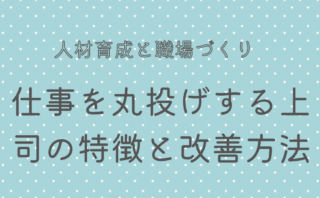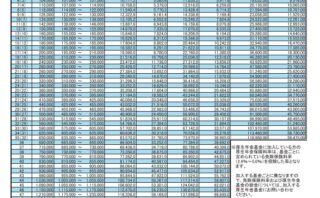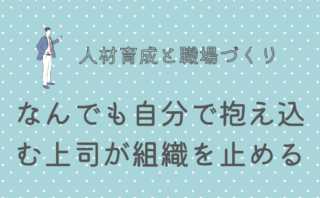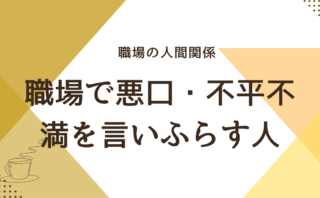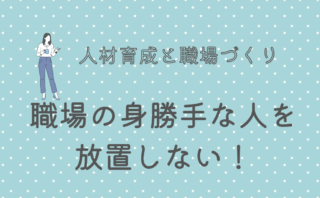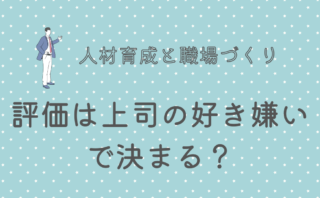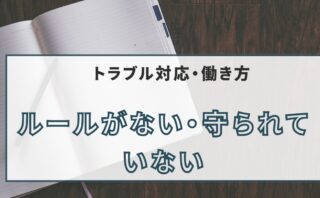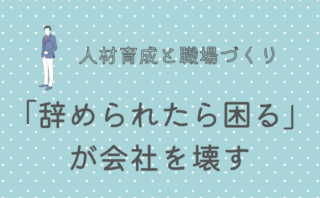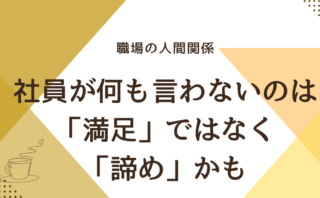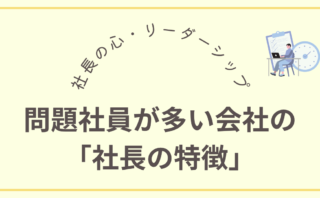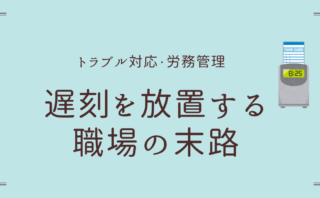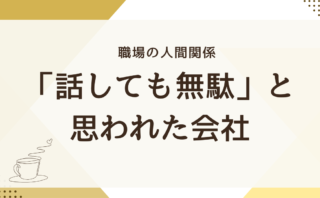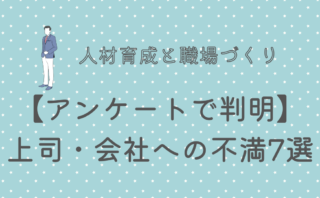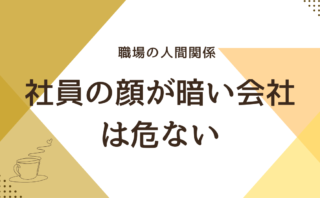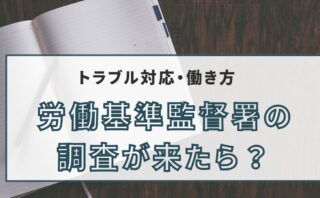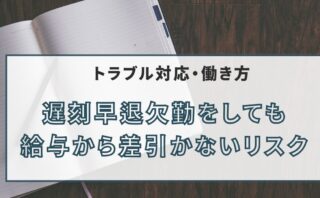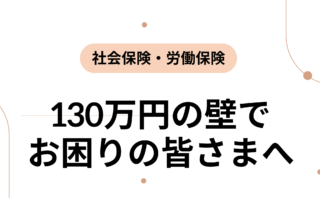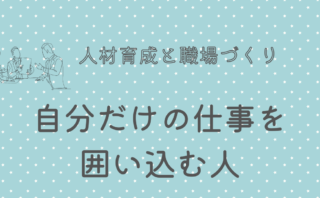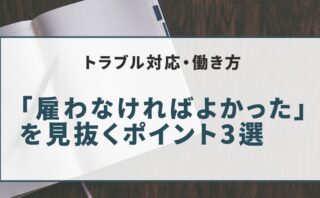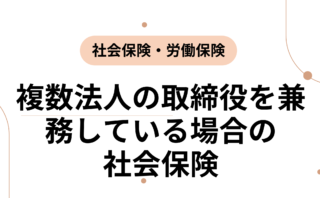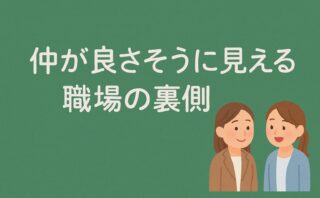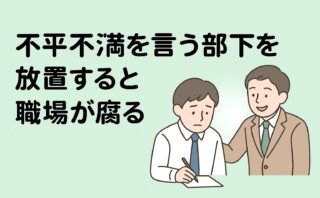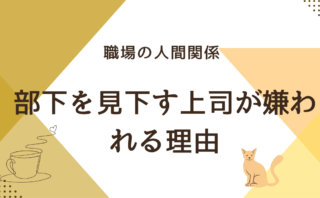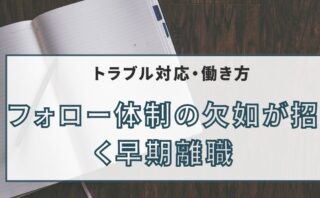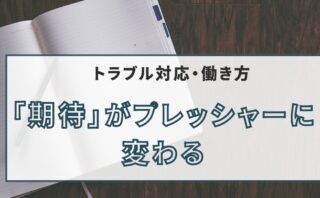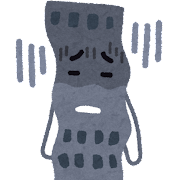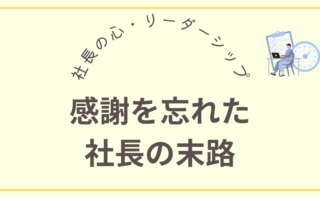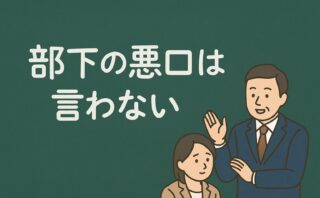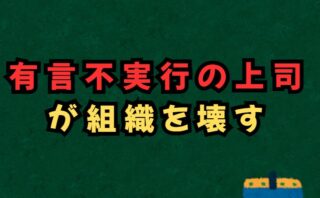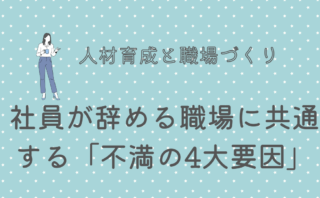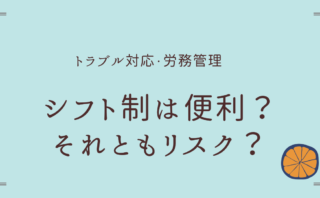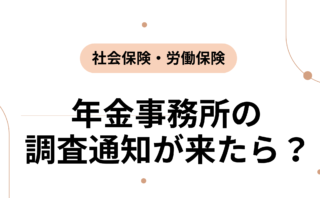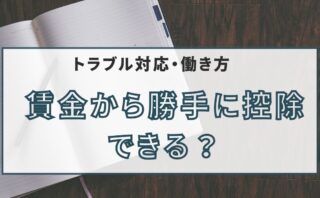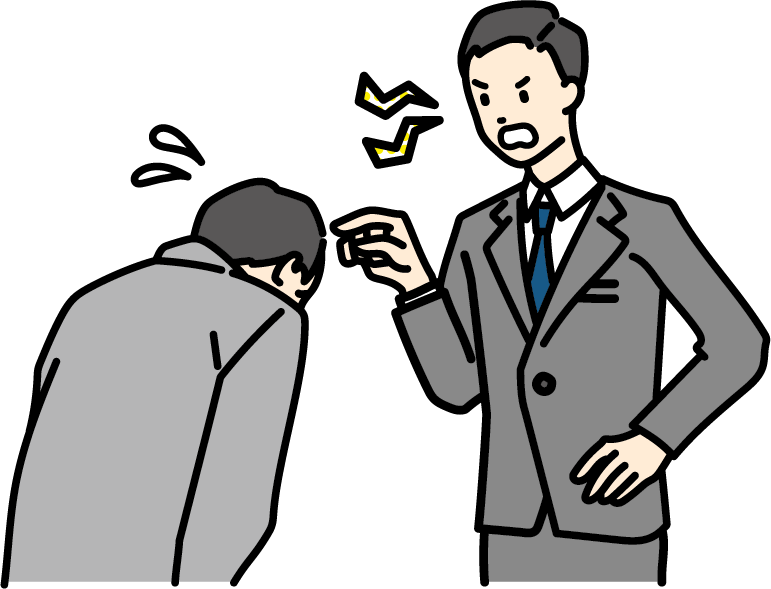はじめに
あなたの会社にもいませんか?
「自分が正しい」と思い込み、周囲の声に耳を貸さない社長。
こうしたトップがいる組織は、部下が萎縮し、組織全体が停滞してしまう傾向にあります。この記事では、そのような社長の特徴と、周囲・組織がとるべき対応策について考えていきます。
「自分が正しい」が口ぐせの社長に共通すること
「自分は間違っていない」
「部下の意見は的外れ」
「自分の経験が正解だ」
このような思考に陥っている社長は、部下の意見を素直に受け取ることができません。どれだけ優秀な社員が意見しても、否定から入ってしまうのです。
結果として、優秀な人材ほど見切りをつけて退職し、イエスマンばかりが残る組織になっていきます。
パワハラ体質が染みついた組織の末路
このタイプの社長は、部下のミスを全て本人の責任にし、頭ごなしに叱責したり、恫喝まがいの指導をしてしまうケースが目立ちます。
すると、社員はミスを恐れて報告や相談ができなくなり、問題が隠蔽される悪循環に陥ります。
組織は徐々に「上司の顔色を伺うだけ」の空気になり、風通しが悪くなります。
その結果、社長はさらに「自分が正しい」と思い込み、誰の声も聞かない強権的なスタイルが加速してしまいます。
対応策:耳の痛い意見にこそ価値がある
この悪循環を断ち切るためには、まず社長自身が立ち止まり、自らを振り返る機会を持つことです。たとえば、
- 社外の第三者からのフィードバックを受ける(コーチ・顧問など)
- 毎月、部下との1on1ミーティングで「改善のヒント」を聞く
- 耳の痛いことも言ってくれる人をあえて周囲に置く
立場が上になるほど、率直な意見は届きづらくなります。
だからこそ、あえてそういった声を大切にできる社長には、人がついていきます。
まとめ:器の大きい社長が、人も組織も育てる
社員に「この人のために頑張ろう」と思わせる社長は、器の大きい人です。
自分の意見だけを押し通すのではなく、他人の意見に耳を傾け、自らの言動を省みる。
そんな社長のもとでは、人材も組織も自然と育っていきます。