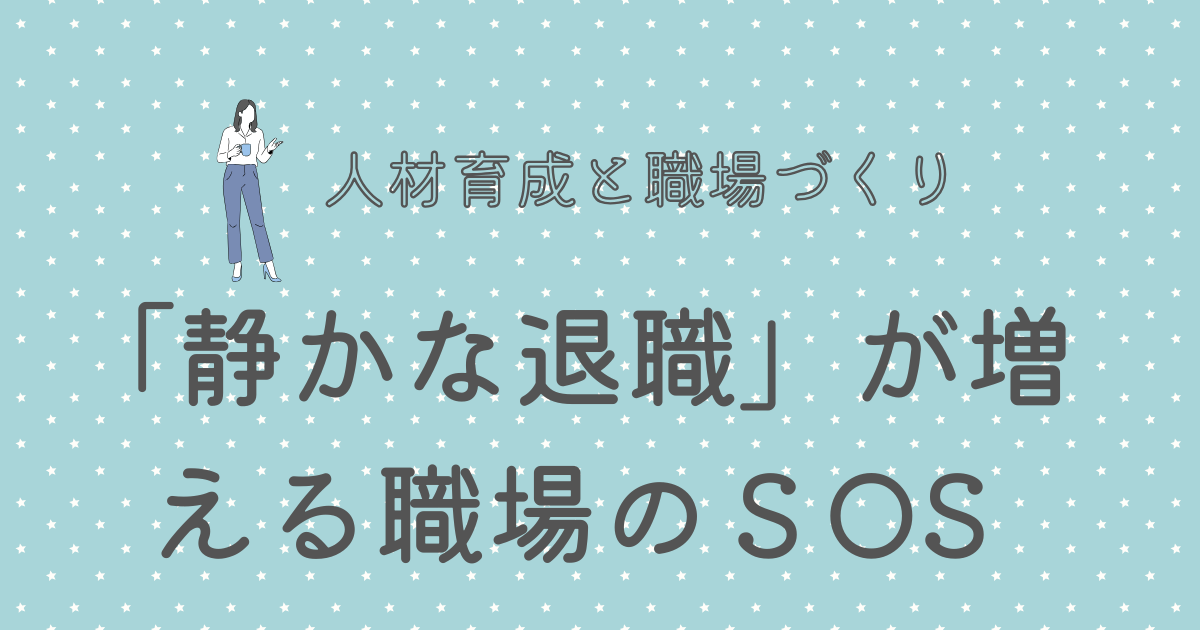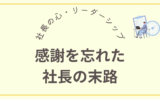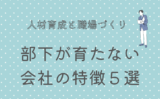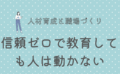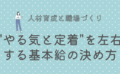あなたの職場は大丈夫ですか?
あなたの周りに、次のような人はいませんか?
- 会議では最小限の発言しかしない
- ランチも一人
- 定時になるとすぐに帰っていく
- 仕事の質は悪くないのに、何か生気がない
怒ってるわけでも、辞めたいと言ってるわけでもない。でも、どこか心が遠い。
それがいま、全国の職場で増えている「静かな退職」です。
4人に1人が感じている静かな退職の気配
リクルートマネジメントソリューションズの最新調査『働く人の本音調査2025』によると、
約4人に1人(27.7%)が「職場に静かな退職者がいる」と回答しています。
仕事はするけれど、気持ちはもうそこにはない。
エネルギーを抑えて働くスタイルです。
あなたの隣の席にも、静かにフェードアウトしている人がいるかもしれませんね。
若手は「恩恵」、中堅は「負担」を感じている
しかし、興味深いのは、年代による受け止め方の違いです。
- 20代はポジティブ
「静かな退職者がいることで相対的評価が上がった」「業務が効率化された」等
(22.3%が恩恵を実感。リクルートマネジメントソリューションズ調べ) - 30~40代・管理職層はネガティブ
「自分の仕事が増えた」「不公平を感じる」と疲弊
静かに辞める人がいると、静かに疲れる人も増える。
これが職場の現実のようです。
静かな退職の原因は、報われなさ?
「最近の若い社員はやる気がない」と言う人もいますが、実際にはやる気が削がれているだけなのかもしれません。
静かな退職の背景にあるのは、次のような積み重ねです。
- 頑張っても報われない
- 意見を言っても、聞いてもらえない
- 改善提案をしても、何も変わらない
人は、報われない時間が続くと、心のスイッチを省エネモードに切り替えます。
それが、「静かな退職」の始まりです。
「報われ感」がある職場は強くなる
同じ調査で、もう一つ興味深い結果が出ています。
それは、
周囲に静かな退職者がいても、成長支援や正当評価を実感している人の幸福感は高い。
つまり、静かな退職を責めるのではなく、
「がんばりが正当に報われる仕組み」があるかどうかがカギのようです。
静かな退職を防ぐには?「静かに成長する職場」に変える
誰だって疲れるときはあります。
モチベーションが下がるときだってあります。
でも大切なのは、そこで「放置」するか「寄り添う」かです。
たった一つの声かけが、職場の空気を変えることだってあります。
「最近、元気がないね。大丈夫?」
「何か困ってることない?」
その一言が、社員を「静かな退職」から「静かな成長」へ導くこともあります。
信頼と対話。それこそが、職場を蘇らせる最強のツールです。
結論:沈黙は諦めではなく、変化を求める声
社員の沈黙は、怠けではありません。
「このままじゃイヤだ」という無言のSOSです。
- 静かな退職は「辞めない退職」。
- 4人に1人がすでに感じている無言のサイン。
- 原因は「やる気の欠如」ではなく「報われなさ」。
- 対策は「叱咤」より「信頼」と「仕組み」。
あなたの職場は、その小さなサインに気づけていますか?
出典:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ『働く人の本音調査2025 第2回』(2025年9月24日公開)
※調査詳細はこちら
編集後記
実は私自身も、かつて勤務時代に「静かな退職」をしていたことがあります。
上司の何気ない一言で、「この会社にいても評価されない」と感じた瞬間がありました。
特に“女性だから”という理由で、意見を聴こうとする姿勢も感じられなかったのです。
その経験がきっかけで、私は社労士を目指しました。
そしていま、当時の“ふつふつとした悔しさ”を、人と職場をつなぐコンサルティングを通じて少しずつ回収しています。
今回の調査結果を見て、あの頃の気持ちがよみがえり、「これは伝えたい」と強く思いました。
この記事は、そんな原点から生まれた一篇です。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。