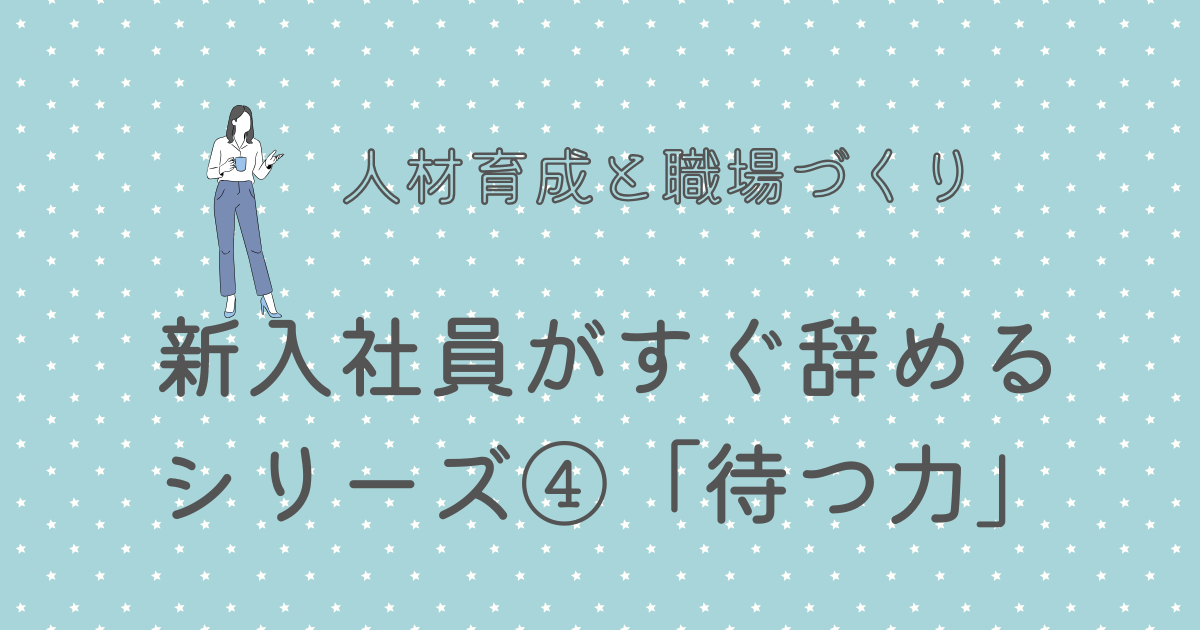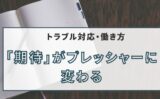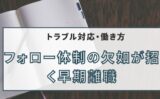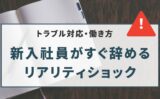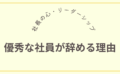はじめに:「また求人…」のループが止まらない
「採用しても3ヶ月もたない」「もう何人辞めただろう」
そんな嘆きを、私は何度も耳にしてきました。
募集 → 教育 → 退職 → 再募集。このループに疲れていませんか?
「今の新人は我慢が足りない」と思いたくなる気持ち、よくわかります。
でも実際は、新人の根性ではなく、上司の怒り方が原因であることが少なくありません。
今回は、怒る上司が待つ力を身につけたことで職場が変わった、ある会社の実例を紹介します。
新人がすぐ辞める原因は「上司の怒り方」にある
神経科学者Arnstenらの研究によれば、人は恐怖の中では学習できないそうです。
怒られている時、脳は「学ぶ」ではなく「逃げる」モードになっています。
これが「怒られた内容を覚えていない」「同じミスを繰り返す」の正体です。
怒る上司がいる職場では、
- 新人が質問できない
- ミスを隠すようになる
- 萎縮して本来の力が出せない
結果として、「この人の下では成長できない」と見切りをつけて退職します。
実例:怒る上司が変わったら新人が定着した話
ある食品卸売業(従業員5名)では、新人が三か月以内に次々と辞めるという悪循環が続いていました。
教育担当のK課長は、
- 営業成績トップ、数字は誰よりも上げる
- 「自分はこうやってきた」という成功体験が強い
- 新人を自分と比較して、できないと厳しく当たる
新人たちの声(退職面談より)
- 「K課長と比べられて辛かった」
- 「自分には向いていないと思った」
- 「怒られすぎて、何が正しいのか分からなくなった」
社長が気づいた「このままでは潰れる」瞬間
社長も当初は「今の新人は根性がない」と考えていました。
しかしある日、衝撃的な事実に気づきます。
- 2年で新人6人が退職
- 5人の会社で常に求人中
- 現場の士気は低下、顧客対応にも支障
「このままでは、人がいなくなって会社が回らなくなる」
その危機感から、社長はK課長と本気で向き合いました。
社長:「Kさん、なぜそんなに怒ってしまうんですか?」
K課長:「怒ってるつもりはないんです。ただ、自分ならできたのにって思って…」
社長:「でも、新人はKさんじゃない。比較されて、『この仕事に向いてない』と言って辞めてますよね」
この対話が、K課長の変化のスイッチになりました。
K課長が実践した「待つ力」
翌日からK課長は、3つのルールを自分に課しました。
- イライラしたら6秒数える→ 感情の波が収まる時間をつくる。
- 爆発しそうな時は、その場を離れる→ 物理的に距離を置く。
- 期待値を紙に書いて貼る(「6ヶ月で一人立ち」と設定し、焦りを抑える。)
最初の1ヶ月は我慢の連続。それでも、少しずつ空気が変わり始めました。
変化の軌跡:半年後の職場に起きたこと
1ヶ月目: 新人は不安そう。K課長は毎日が我慢の連続。
2ヶ月目: ミスをしても、K課長は怒らず一緒に対応。
3ヶ月目: 新人が自分から相談に来るようになる。
半年後: 新人2名、全員定着。
1年後には、辞めた元社員から「戻りたい」との連絡まで。
K課長:「変わってよかった…」
待つ力が生んだ、心理的安全性
怒りを抑えたことで、職場には安心して話せる空気が戻りました。
部下は笑顔で報連相をし、ミスを共有できるチームへ。
Googleの研究によると、成果を上げるチームに共通するのは「心理的安全性」があること。
つまり、「待つ力がある上司」は、「部下が力を発揮できる環境」をつくれるリーダーなのです。
「待つ力」こそ、最大のマネジメント
K課長はこう語ります。
「今は待つことの大切さが分かりました。焦って叱るより、信じて任せた方が、みんなが自分から動いてくれるんです。」
教育とは、相手を自分の型にはめることではなく、その人のペースで成長を見守ること。
急がず、信じて待つ力が、部下を育て、チームを強くします。
あなたの職場は大丈夫ですか?
もし、あなたの職場で
- 新人がすぐ辞める
- 若手が萎縮している
- 上司が「自分基準」で厳しく怒る
もし一つでも当てはまるなら、今日からできることがあります。
- イライラしたら6秒数える
- 爆発しそうな時は、その場を離れる
- 期待値を紙に書いて、見える化する
完璧を目指す必要はありません。まずは、ひとつだけ試してみてください。
チームは変わり始めます。
まとめ
怒りを我慢するのではなく、待つ力で人を育てる。
それは「優しさ」ではなく、戦略的なリーダーシップです。
人が定着する職場とは、信じて待てる上司がいる職場ではないでしょうか。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。