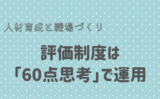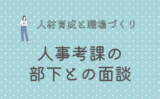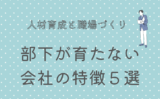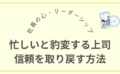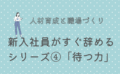はじめに:「研修を受けさせたのに、何も変わらない」
「せっかく外部研修に参加させたのに、現場では何も変わらない」
そんな声を、経営者や管理職からよく聞きます。
研修の内容が悪いわけではありません。
多くの場合、“受けさせる”ことに満足してしまい、“活かす仕組み”がないのです。
実は、「学ぶ」と「変わる」の間には、大きな溝があります。
その溝をどう埋めるか。ここが人材育成の本当の勝負どころです。
研修が活きない3つの理由
多くの企業で、研修が十分に活かされていない原因は以下の3つです。
- 目的が曖昧
「とりあえず受けてきて」では、受講者は受け身になります。何を持ち帰るべきか分からないまま、ただ時間を過ごすだけになりがちです。 - 研修後のアクションがない
学んだ内容を「どう使うか」が設計されていないと、知識は数日で風化します。
「良い話だった」で終わってしまうのです。 - 現場に戻ると元通り
本人が意欲的でも、周囲が何も変わっていなければ続きません。
「一人だけ浮くくらいなら、前のやり方に戻ろう」と思ってしまうのです。
研修を行動変化につなげる3ステップ
【ステップ1】研修前:目的とミッションを明確にする
研修に送り出す前に、必ず以下を伝えましょう。
✓ なぜこの研修を受けるのか(目的)
例:「お客様対応の質を上げるため」「チームリーダーとしてのスキルを身につけるため」
✓ 研修後に何をしてもらうか(ミッション)
- 「来週の朝礼で、学んだことを5分間発表してもらいます」
- 「研修内容をもとに、業務改善案を1つ提出してください」
- 「1ヶ月後の会議で、実践した結果を報告してもらいます」
人は「誰かに伝える」と分かっているとき、学び方が変わります。
ただ聞くのではなく、「どう説明しようか」と考えながら受講するようになるのです。
【ステップ2】研修直後:説明させて定着させる
研修から戻ったら、最初の1週間に以下を実行しましょう。
- 学んだことを他の人に説明させる
・「説明する=復習」になり、理解が一気に深まる - 学びを使った小さな課題に取り組む
・「今週、お客様から“ありがとう”を3回もらう接客をしてみよう」
「鉄は熱いうちに打て」 です。研修直後の「やる気」と「新鮮な記憶」があるうちに、実践の機会を作りましょう。
【ステップ3】研修後1〜3ヶ月:振り返りで習慣化
一度のアウトプットで終わらせず、定期的に育成サイクルを回します。
月次ミーティングでの確認項目:
- 実践できたことは?
- どんな成果が出たか?
- 続けるために必要な支援は?
このサイクルを回すことで、「知識 → 行動 → 習慣」に変わっていきます。
研修定着の壁:移行期コストをどう乗り越えるか
仕組みを導入すると、最初は「めんどう」「そこまでしなくても」といった抵抗が出ます。
しかし、ここでやめてしまうと、また研修が風化する職場に戻ります。
ポイントは、「少しずつ定着させる」こと。
- 最初の3ヶ月は、1テーマだけ繰り返す
- 無理に評価へ結びつけず、「共有の場」として続ける
- 成果が出た事例を全社で共有し、続けた人が得をする流れを作る
定着には時間がかかりますが、継続できた組織ほど、研修効果が確実に積み上がります。
最後に:現場を変えるのは「仕組み」
研修効果の差は、研修講師の質ではなく、上司のフォロー体制で決まります。
■自己チェック
- 研修前に「期待する成果」を伝えていますか?
- 研修直後に「実践の場」を作っていますか?
- 定期的に「振り返り」をしていますか?
この3つを回せば、研修はイベントから育成の仕組みへと進化します。
研修は、受けさせて終わりではなく、現場で「芽を出す仕組み」こそが本番なのです。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。