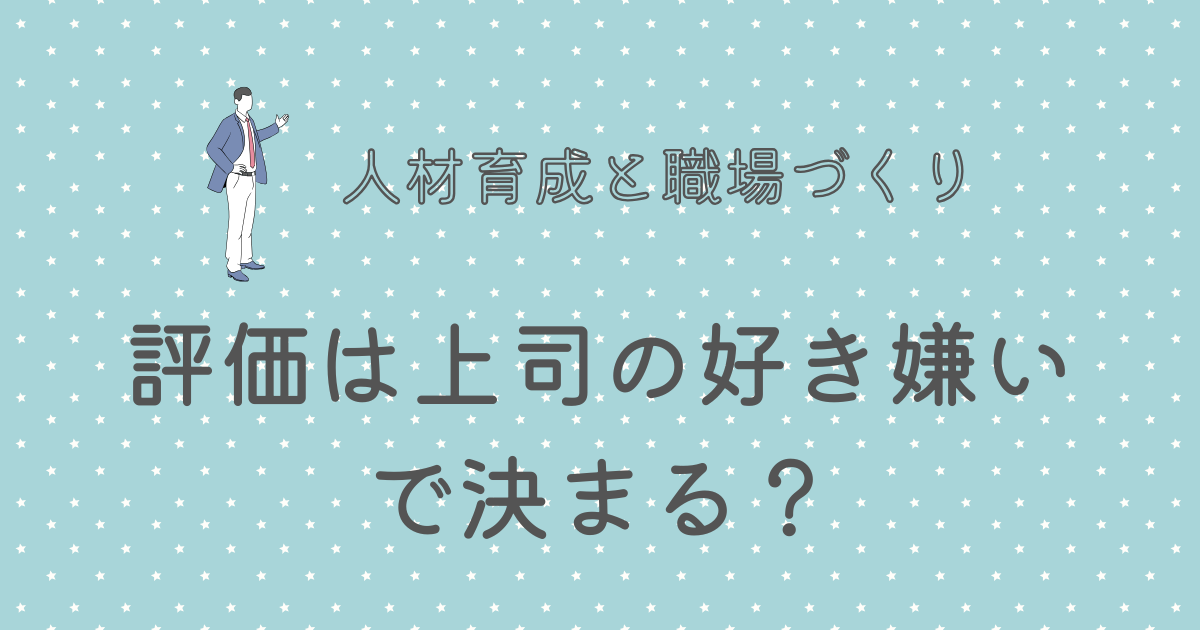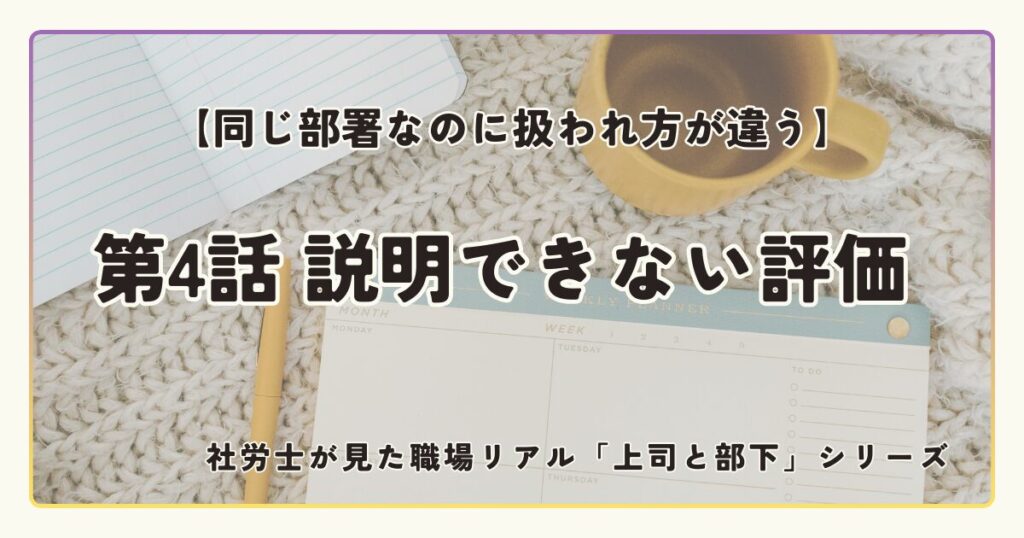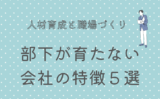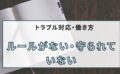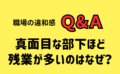はじめに:上司だって悩んでいる
管理職研修をしていると、よく出てくる言葉があります。
「正直、これまで好き嫌いで評価してたかもしれません」
そう、これはどの職場でも起きている“あるある”です。
上司も人間です。合う・合わない、話しやすい・頼みにくい……。
感情が入り込みやすいのが“評価”というものです。
しかし、その「ちょっとした感情のズレ」が、部下にとっては“信頼を失うきっかけ”になります。
1.「評価に納得できない」と部下はどう動くか
部下が「好き嫌いで評価された」と感じると、その瞬間から職場の空気が少しずつ変わり始めます。最初は、「たまたま低くつけられたのかな」と思う程度。でも、それが続くとこうなります。
- 消極的になる:「言われたことだけやればいい」となる
- 転職を考える:「努力しても報われない」と感じる
- 同僚に不満を広げる:「どうせ上司の好き嫌いで決まる」と噂になる
この“好き嫌いフィルター”が広がると、上司への不信がチーム全体に伝染します。
結果、報告が減り、協力が減り、会話が減る。気づいたときには、職場の温度がすっかり下がっているのです。
2. 「納得できる評価」は、厳しくても信頼につながる
おもしろいことに、どんなに厳しい評価でも、納得感があれば不満は出ません。なぜなら人は、「感情」ではなく「理由」に納得したいから。
「今回はここが弱かった。次はこうすれば上がるよ」
このように、具体的な理由と改善策がセットであれば、部下は「自分を見てくれている」と感じます。
逆に、理由が説明できない評価は、どんなに点数が良くても“信頼”にはなりません。
3. 感情を排除する最強ツール:人事考課表の使い方
評価に感情を持ち込まないためには、仕組みでブレを防ぐしかありません。
その代表が、「人事考課表(評価シート)」です。
ただし、持っているだけでは意味がありません。大切なのは“どう使うか”です
考課表の運用3ステップ
- 期初に評価項目を共有する
→ 「どんな行動が評価されるのか」を部下と話し合う。 - 途中でも進捗面談を設ける
→ 年1回の評価では遅い。途中で方向修正できる仕組みに。 - 評価時には必ず具体例を挙げる
→ 「〇月の案件でこう動いたね」と、事実ベースで伝える。
こうした運用で、評価が「一方的なジャッジ」ではなく、“対話のツール”として機能します。
4. 管理職に必要なのは「感情管理スキル」
どんなに制度を整えても、最後に判断するのは“人”です。
だからこそ、管理職自身が自分の感情に気づく力を育てる必要があります。
次のような意識を持つだけでも、評価のブレは大きく減ります👇
- 「この評価に、個人的感情が混ざっていないか?」と自問する
- 他の管理職と評価を擦り合わせる会議を行う
- 自分の評価理由を言語化し、客観的に振り返る
評価スキルとは、“他人を見る力”ではなく、“自分を見直す力”でもあるのです。
5.評価は「点数づけ」ではなく「信頼づくり」
評価は、結果を伝える場ではなく、「これからどう成長していくか」を共有する時間です。
- できたことを言語化して認める
- 改善点は、次のチャンスにつなげる形で伝える
その積み重ねが、部下のやる気と信頼を育てます。
まとめ
人は感情の生き物。意識しなければ、評価には“好き嫌い”が入り込みます。
だからこそ、
- 仕組み(人事考課表)で公平性を担保し、
- 意識(感情管理)で偏りを減らす。
そして、部下が「見てもらえている」と感じる評価こそが、信頼と成長を生む評価です。
感情ではなく、事実と対話で伝える評価を心がけたいですね。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。