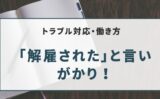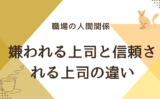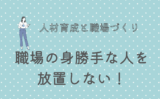はじめに
「顧問社労士はいるけど、本当にこの判断でいいのか不安…」
「別の社労士の意見も聞いてみたい」
実はこうしたお問い合わせ、少なくありません。
医療でセカンドオピニオンがあるように、労務の世界でも「他の視点を聞いてみたい」というニーズは確実に増えています。
どんなときにセカンドオピニオンが必要?
どういうときにセカンドオピニオンを求められたかといいますと、
- 解雇トラブルが長引き、解決の糸口が見えない
- 顧問社労士のミスが多いのに謝らない
- アドバイスがあまりに簡潔で、逆に不安が残る
- トラブルになると「弁護士に相談してください」と突き放される
「顧問社労士の言っていることは正しいのか?」
「他の選択肢はないのか?」
経営者として当然の疑問です。
セカンドオピニオンの対応策
ご相談の中には、実は単なるコミュニケーション不足 というケースもあります。
その場合は「いまの思いを率直に顧問社労士に伝えてみては?」とアドバイスします。
一方で、別の視点や選択肢を探したい場合には、私からもセカンドオピニオンとして具体的な提案を差し上げます。
セカンドオピニオンの意義
セカンドオピニオンは 「顧問社労士を否定するため」ではありません。むしろ、複数の視点から判断材料を得ることで、より納得感のある意思決定ができるのです。
経営判断に迷いはつきもの。
だからこそ「別の角度からの助言」を取り入れるのは自然なことだと思います。
私自身の学び
セカンドオピニオンをお受けする中で、私自身も「自分のアドバイスは独りよがりになっていないか」と常に振り返るきっかけをいただいています。
社労士にとっても、経営者にとっても、セカンドオピニオンは成長の機会 です。
まとめ
- 顧問社労士がいても「他の意見を聞きたい」と思うのは自然
- セカンドオピニオンは顧問との関係を壊すものではなく、判断材料を増やすための手段
- 経営者にも社労士にも、新しい気づきを与えるきっかけになる
「この判断で本当にいいのか?」と迷ったとき、セカンドオピニオンを選択肢のひとつに入れてみてはいかがでしょうか。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。
状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。