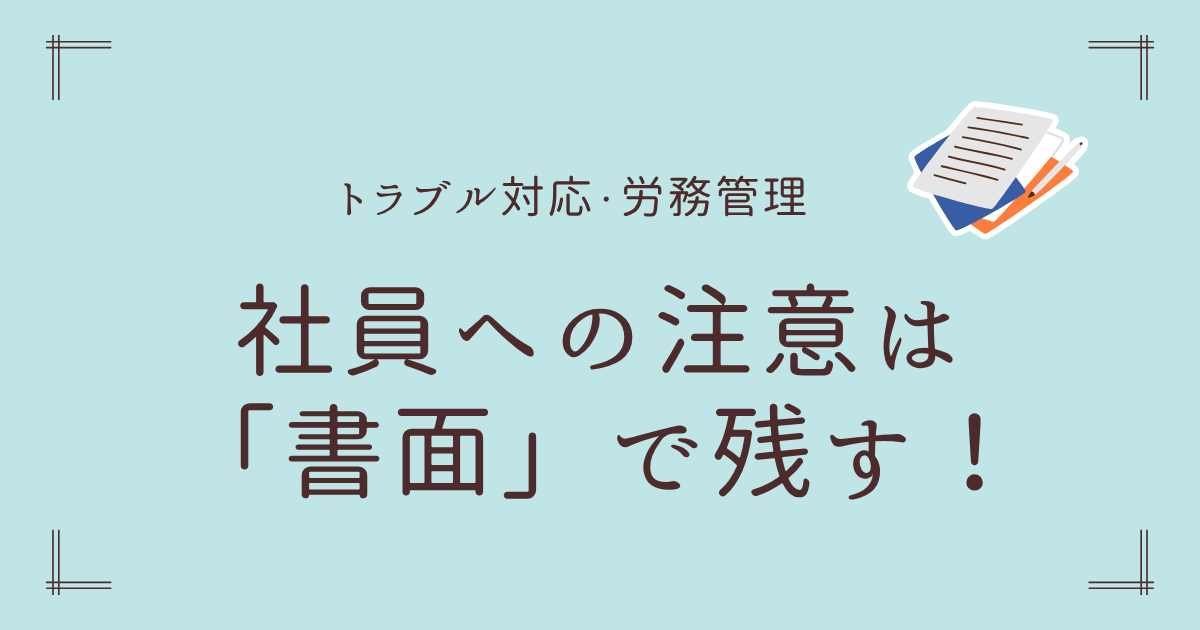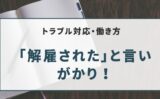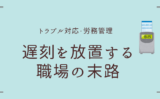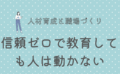はじめに:口頭注意だけでは会社は守れない
「そんなこと言われていない!」「証拠を出せ!」
社員への注意が、後に裁判や労基署調査に発展すれば、最悪の場合、数百万円単位の残業代請求や慰謝料を支払う羽目になることもあります。
「口頭だけの注意」は、実は 最も危険な対応 です。
トラブルから会社を守るカギは、注意を書面で残すことにあります。
1.口頭注意だけが招く「3つの最悪シナリオ」
- 裁判で敗訴
「注意した証拠がない」と判断され、会社側が不利になる。 - 労基署からの指摘
「記録がない=管理放棄」と見なされ、是正命令・長期調査・社名公表のリスクに直結。 - 職場崩壊
問題社員が開き直り、周囲の社員が不満を募らせ離職につながる。
2.正しい注意指導のステップ
感情的に叱るのではなく、段階を踏んだプロセスが重要です。
- 第1段階:口頭で注意(ただし社内記録を書面で残す)
- 第2段階:改善がなければ書面で注意指導
- 第3段階:それでも改善しなければ警告書(懲戒処分の可能性を明示)
この流れを守ることで、公正で一貫性のある対応となり、証拠力も高まります。
3. 書面が持つ「教育」と「防衛」の力
書面指導には2つの大きな効果があります。
- 教育効果
社員本人が「正式に注意された」と自覚し、行動を改めやすくなる。 - 防衛効果
トラブルが裁判や労基署調査に発展した際、会社を守る強力な証拠となる。
「教育」と「防衛」の両輪が揃うのは、書面化だけです。
【参考】書面指導の実践ポイント
書面に残す際は、次の点を必ず盛り込みましょう。
- 問題行動の事実(何をしたのか)
- その行動の背景や経緯
- 業務や顧客・同僚への悪影響
- 本人の反応(反省したか、反発したか)
さらに、改善状況をチェックリスト化し、定期的に確認すると効果が高まります。
4. 抵抗・再発する社員への対応
それでも反発や再発を繰り返す社員には、次の対処を。
- 「自分はちゃんとやっている」と反論されたら
→ 書面記録でこれまでのミスや迷惑行為、会社に生じた損害や影響を淡々と示す - わざとトラブルを起こされたら
→ 証拠を積み上げ、懲戒や解雇に備える - 本人に適性がない場合
→ 昇給・評価は見込めないと説明し、淡々と退職を促す
5.紛争リスクに備える「証拠」としての書面
万が一、紛争になったときは、書面の記録が最大の武器になります。
- 「この社員には改善の余地がなかった」
- 「労使間の信頼関係はすでに破綻していた」
これらを客観的に示せれば、会社側に有利な判断が下される可能性が高まります。
まとめ:書面で残すことが会社を救う
- 口頭注意だけでは 裁判・労基署・高額賠償 のリスクが残る
- 書面化は「教育」と「防衛」の両方で効果を発揮する
- 今日からできることは、注意指導のチェックシートや簡易フォーマットを用意して、必ず記録に残す習慣 をつくること
書面で残す。たったそれだけで、社員を育て、会社を守ります。
経営者にとっての最強のリスク回避策です。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士 竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。