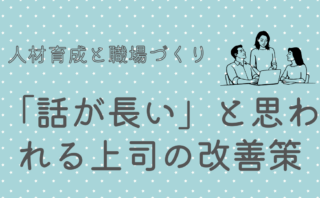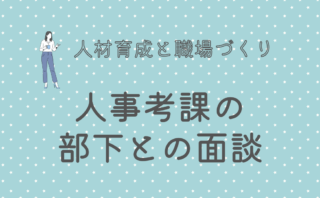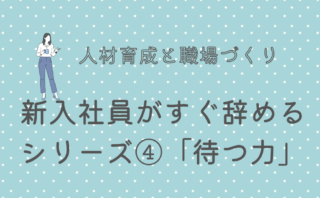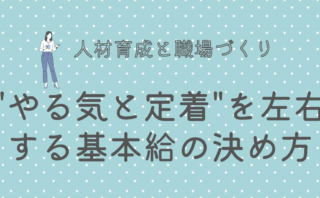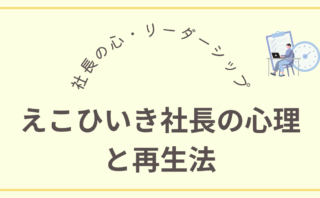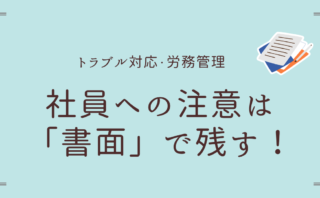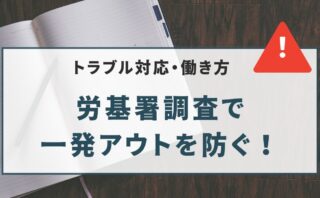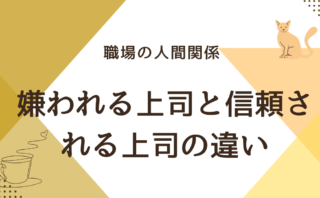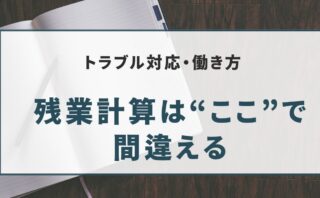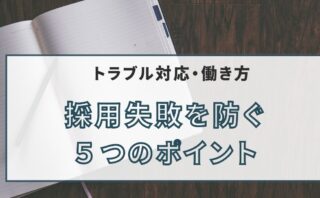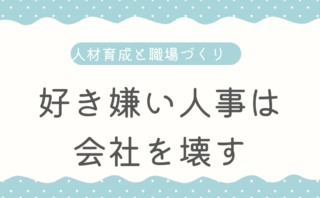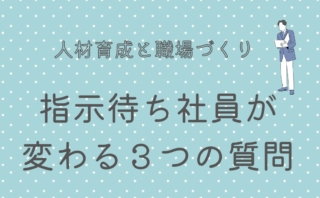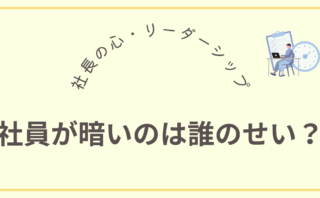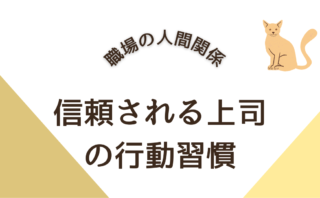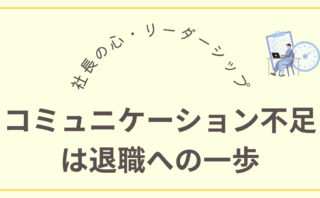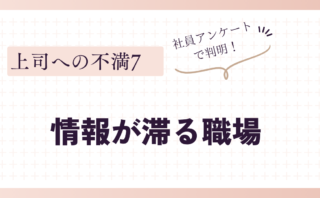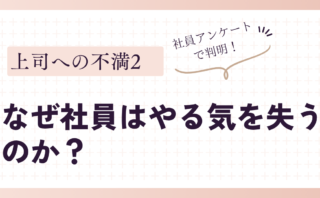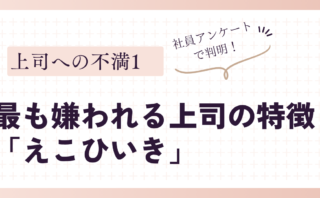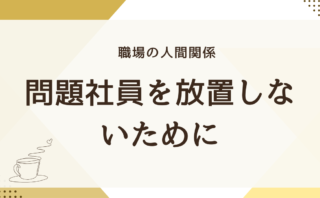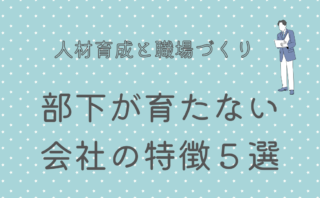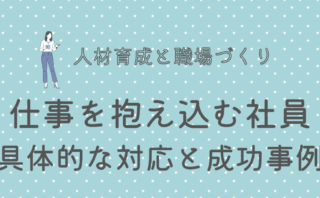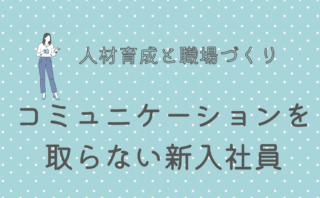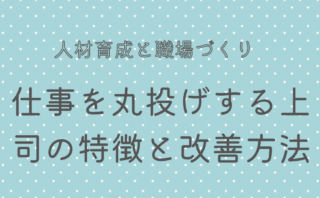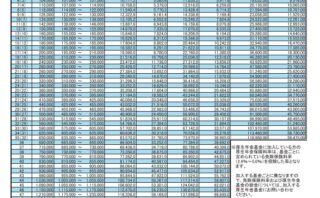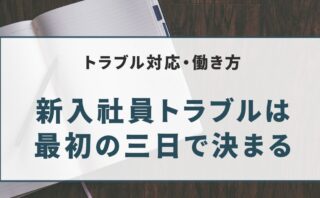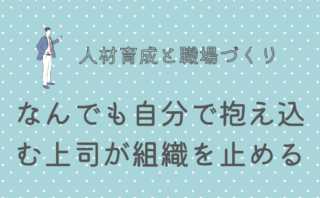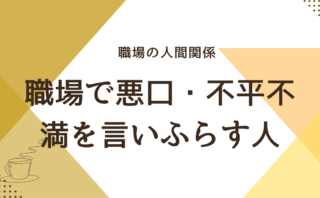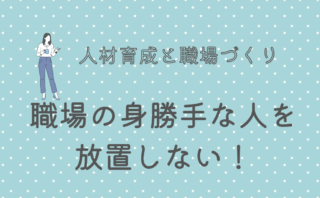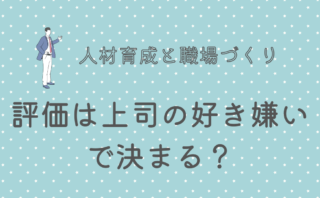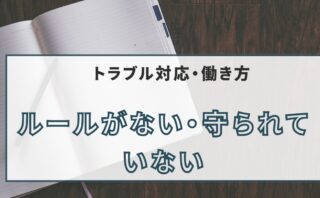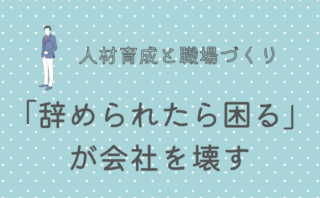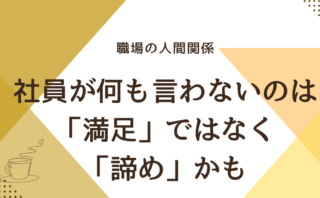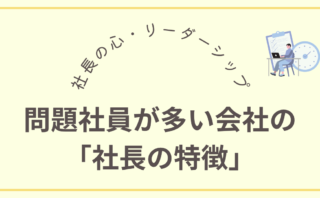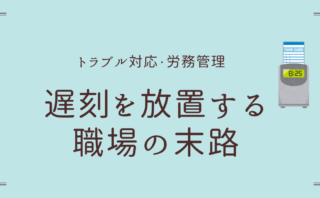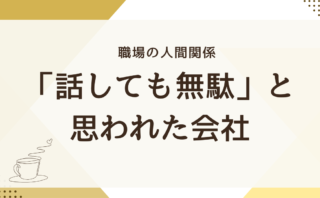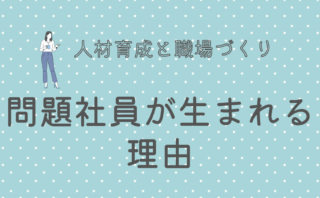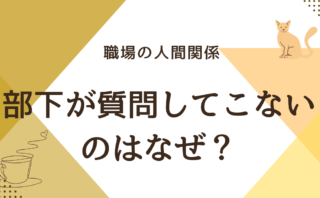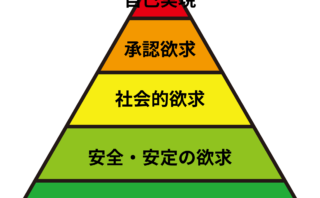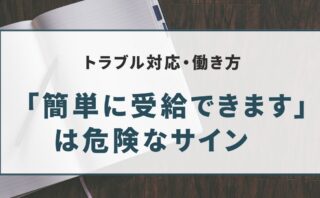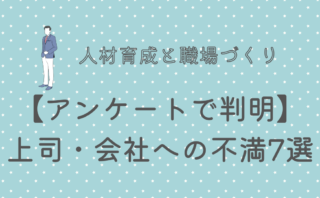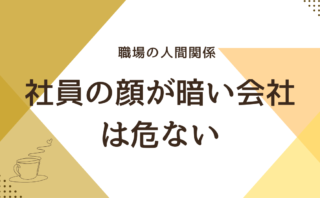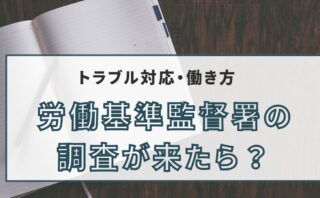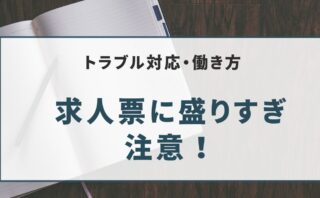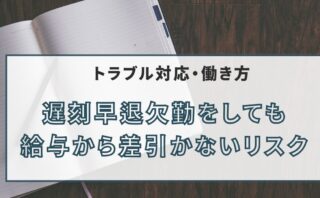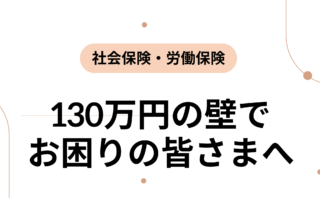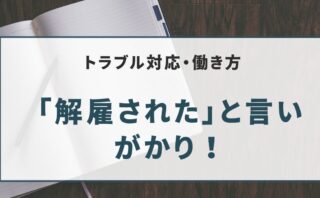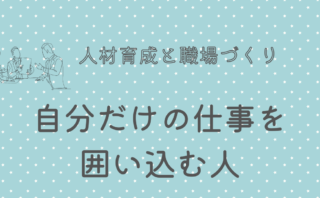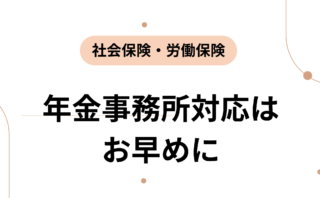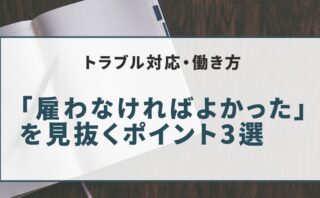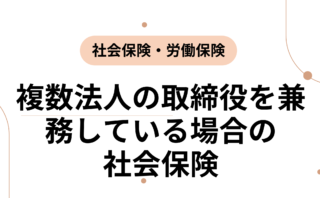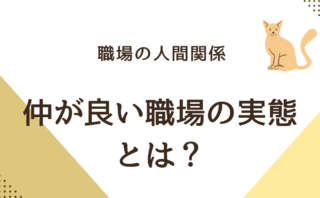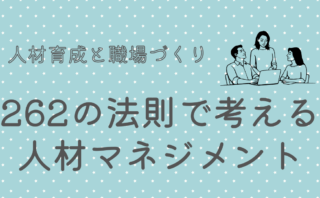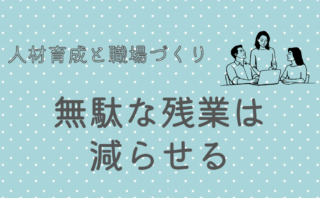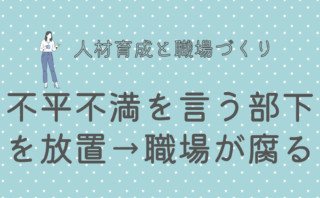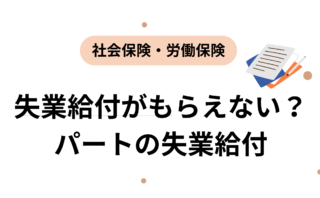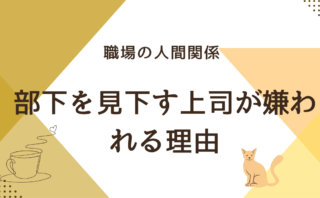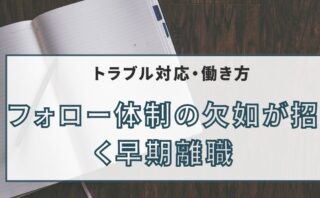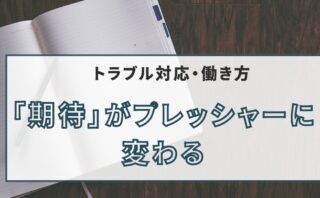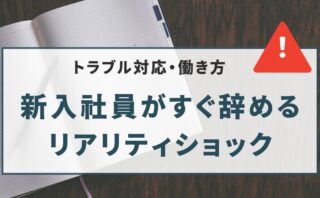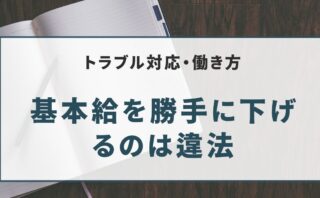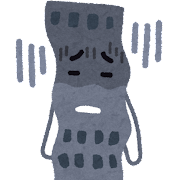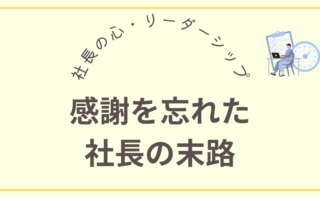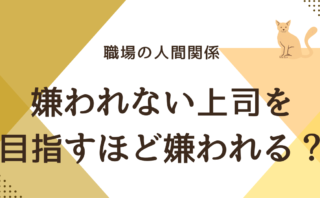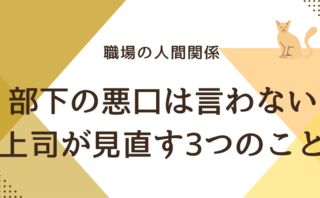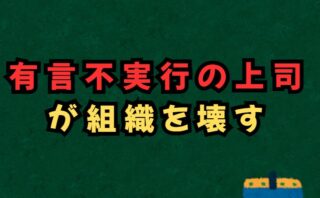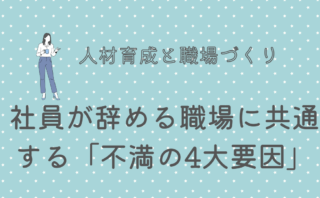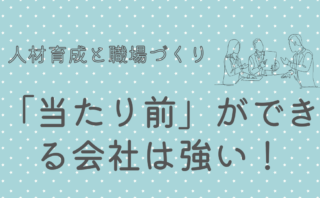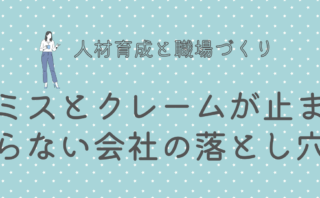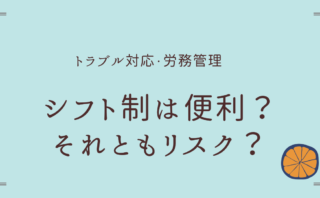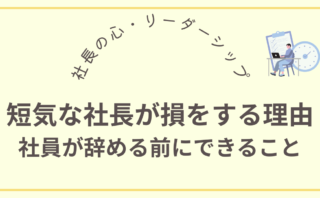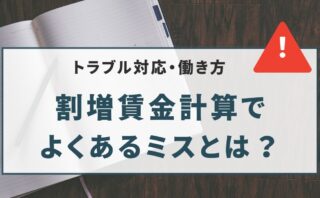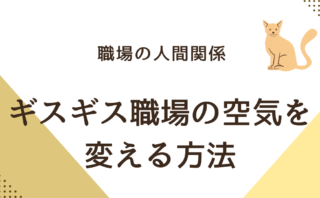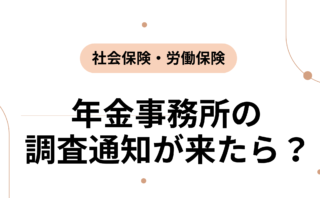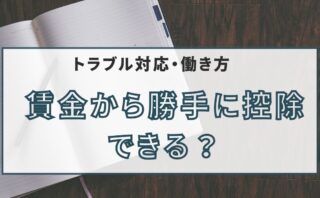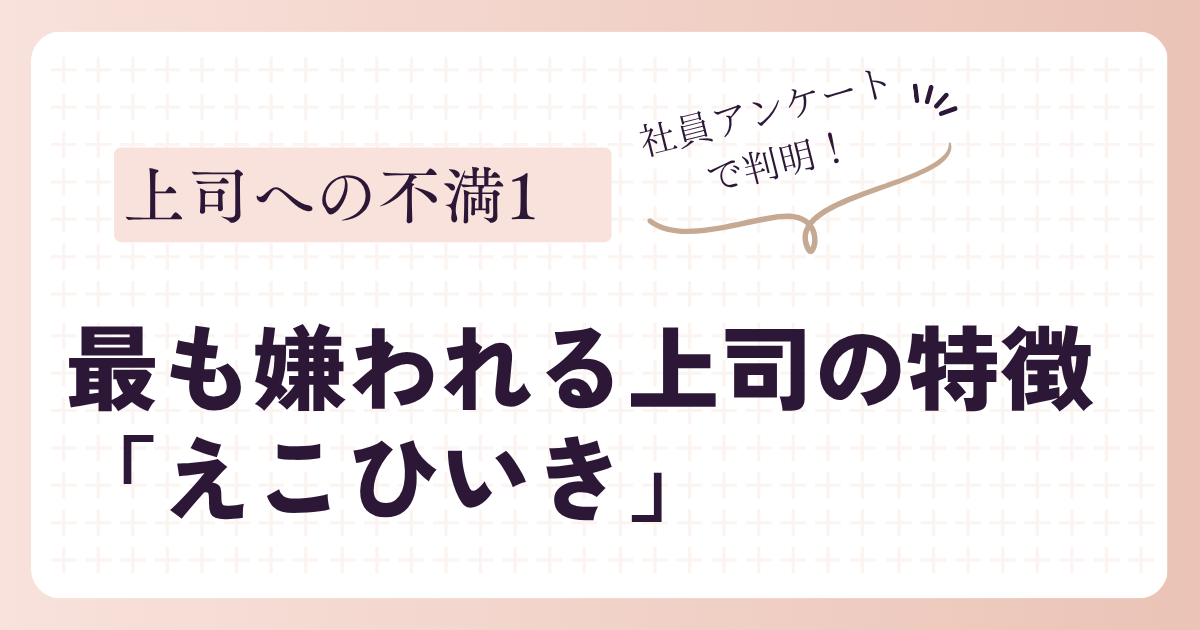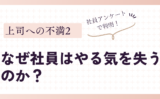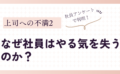はじめに
「上司に対する不満」は、社員アンケートの中でも常に上位に挙がるテーマです。
なかでも目立つのが、「対応が人によって違う」「えこひいきがある」という声。
第1回のテーマは、「公平さを欠いた対応=えこひいき」です。
気に入った部下には甘く、そうでない人には厳しい。そんな態度は、職場全体に悪影響を及ぼします。
今回は、「不公平な上司」が職場に与える影響と、企業としての改善策について考えていきます。
不公平な上司の典型パターン
こんな場面に、心当たりはありませんか?
- 気が弱い人には厳しく叱るが、お気に入りや強く反発するタイプには何も言わない
- 同じミスでも、叱る人・叱らない人が明らかに分かれている。
つまり、相手によって態度を変える上司です。
こうした不公平な対応は、部下の信頼を失うだけでなく、「この上司の下で頑張っても報われない」という空気が広がり、チーム全体の士気を下げてしまいます。
不公平がもたらす職場への悪影響
不公平な態度が続くと、職場には以下のような悪循環が生まれます。
- 部下が腐ってしまい、仕事の質が低下する
- 「どうせ評価されない」という諦めから、自分本位な行動が増える
- チームワークが崩れ、助け合いがなくなる
- 問題が起きると責任の押しつけ合いになる
- 職場の雰囲気が悪化し、離職率が上昇する
こうした「えこひいき」は個人の好き嫌いの問題に見えて、実は組織全体の公平性や透明性を揺るがす深刻な問題に発展します。
問題は上司だけではなく、会社の体制にもある
このような上司を放置している企業側にも責任があります。たとえば、
- 管理職への研修・教育が不十分
- 問題行動に対して注意・降格などの対応がなされていない
といった可能性が考えられます。
現場任せで問題を放置するのではなく、組織として問題に向き合い、改善に取り組む姿勢が必要です。上司個人に責任を押しつけるだけでは、どれだけ人が辞めても原因に気づけないままになります。
企業がとるべき具体的な対策
- 管理職に対する「評価・指導スキル」の育成
管理職には業績管理だけでなく、公平に人を評価・指導するスキルが求められます。
感情的な対応を避け、冷静に接する力を育むために、研修やコーチングを定期的に実施しましょう。 - 現場の声を拾い上げる仕組みづくり
従業員アンケートや1on1ミーティングなどを活用して、現場の声を継続的に拾い上げましょう。「風通しの良さ」は、トラブルを未然に防ぐ鍵になります。 - 人事登用の基準を見直す
「仕事ができる人」が「良い上司」になるとは限りません。公平性・人間力・リーダーシップといった観点を、昇進の基準にしっかりと組み込む必要があります。
まとめ
「公平な対応」は、信頼される上司の基本条件です。それができない管理職を放置すれば、チームの力は発揮されず、職場の空気も悪化します。
「人が辞める理由の多くは、仕事内容ではなく上司」です。この事実に向き合い、会社として改善を進めることが求められます。
次回予告
次回は、「評価が見えないこと」について掘り下げます。