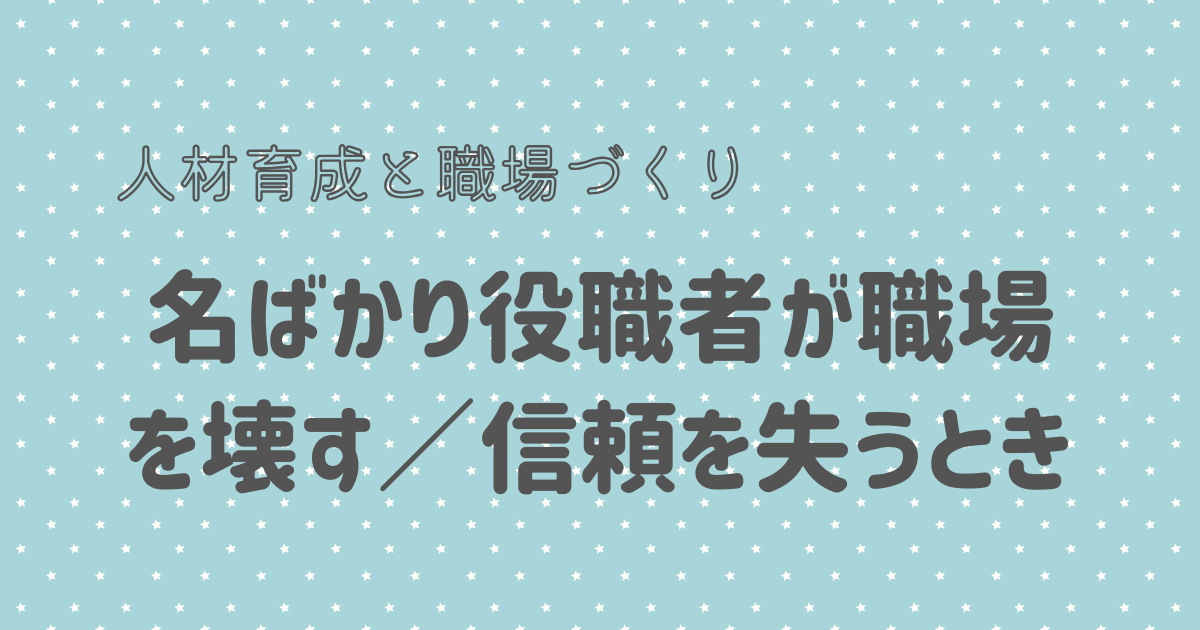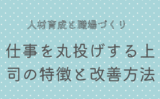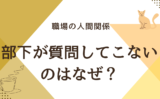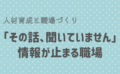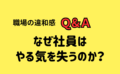はじめに
「その肩書き、本当に意味がありますか?」
これは、表に出ない現場の本音です。
部下は、思っている以上に上司を見ています。
- 肩書きではなく、行動を
- 役職手当ではなく、覚悟を
そして、気づいています。責任を取らない上司のことを。
上司なのに、決めない
会議で意見は言う。でも、最後の判断はしない。
「みんなで考えよう」
「様子を見よう」
その言葉の裏で、決断は先送りされます。
失敗したときだけ、「現場の判断だ」と逃げる。
部下は思います。この人は、私たちを守らない。
信頼は、その瞬間から崩れていきます。
手当はある、責任はない
役職者なのに、
- 部下の育成をしない
- 問題社員に向き合わない
- 不公平を正さない
- 矢面に立たない
それでも、役職手当はつく。
現場は敏感です。「なぜあの人が上にいるのか?」
この疑問が生まれたとき、組織の空気は確実に変わります。悪い方に。
部下が本当に求めているもの
部下は、完璧な上司を求めているわけではありません。
失敗してもいい。迷ってもいい。でも、
- 逃げない人であってほしい
- 決めるときは決める人であってほしい
- 守るときは前に立つ人であってほしい
それだけです。
役職とは「覚悟」の名前
役職は、席の場所ではありません。責任を引き受けるという宣言です。
上司とは、
- 決断する人
- 矢面に立つ人
- 部下を育てる人
- 不公平を正す人
その覚悟に対して支払われるのが、役職手当です。
放置すれば、組織はどうなるか
名ばかり役職者がいる職場では、
- 優秀な人ほど静かに去る
- 挑戦する人ほど諦める
- 誰も上を目指さなくなる
そして最後に残るのは、責任を避ける空気です。
組織は、ゆっくりと弱くなっていきます。
上司という立場に立つということ
役職はゴールではありません。スタートです。
「上に立つ」ということは、楽になることではなく、重くなることです。
その重さを引き受けたとき、初めて人は、上司になります。
肩書きではなく、行動で。
言葉ではなく、覚悟で。
職場を変えるのは、制度ではなく、その立場にいる人の自覚です。
経営者の方へ
名ばかり役職者は、本人だけの問題ではありません。
- その人を役職に就けた判断
- その状態を是正しなかった仕組み
- 役割と評価が曖昧な制度設計
それらは、組織の構造そのものの問題です。
「うちに名ばかり役職者はいないか」ぜひ一度、見直してみてください。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたらお気軽にご相談ください。
📖 関連コンテンツ
職場の人間関係や、人が辞める理由を、
ドラマ形式で描いた連載を、noteで公開中です➡
▶︎ 上司部下シリーズ
▶︎ 辞める人たちシリーズなど