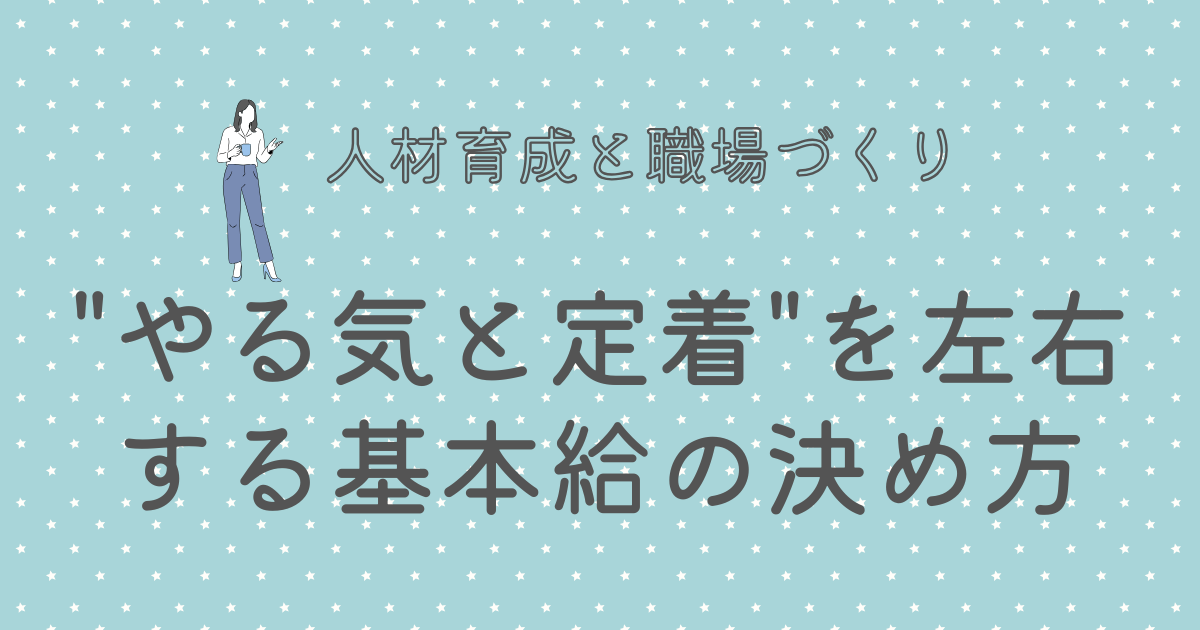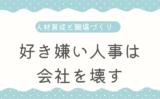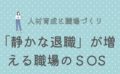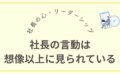はじめに
「求人を出しても人が来ない」
「若手がすぐ辞める」
「昇給が長年止まったまま」
その背景には、基本給の設計ミスが潜んでいることが少なくありません。
基本給は「会社の信頼度」を映す鏡
求職者は求人票の「月給25万円」という数字だけを見ているわけではありません。
その裏にあるメッセージを読み取っています。
- この会社で長く働けば、自分の生活はどうなるのか?
- 努力は報われるのか?
実際、採用の現場でよく聞く声は、
- 「初任給はいいけれど、その後が見えない」
- 「昇給のルールが曖昧で将来が不安」
つまり、人は今の額より上がる仕組みの有無で、会社への信頼を判断しているのです。
中小企業でもできる「伸びる給与設計」
「うちは中小企業だから、大企業のようには上げられない」
そう考える経営者は多いですが、重要なのは金額の多さより納得できる仕組みです。
① 今の基本給を見える化
同じ勤続年数・年齢でバラつきがないか、説明できない差がないかを整理します。
「なぜこの人は他より低いのか」と問われて答えられない状態が、不信感の温床になります。
② 上がる基準を明確に
勤続年数・評価・役職など、どんな行動で昇給につながるのかを数値や言葉で示しましょう。
たとえ金額が小さくても、「努力が報われる」と感じる仕組みがあれば、人は定着します。
③ 将来像を見せる
入社時に「3年後の給与モデル」を提示できる会社は強いです。
「1年目22万円 → 2年目23万円 → 3年目25万円」
これだけで、社員は安心して未来を描けます。
④ 毎年見直す
最低賃金や同業他社の動向を踏まえ、年に1度は基本給体系を点検しましょう。
例:最低賃金が上がったら、全社員の基本給も見直します。
「うちは最低賃金ギリギリの人だけ上げる」では、他の社員の不満が溜まります。
変化に対応できる柔軟さが、社員の信頼を生みます。
まとめ:基本給は経営戦略
基本給は人件費ではなく、採用・育成・定着をつなぐ経営戦略です。
もし今、
- 求人応募が少ない
- 若手が続かない
- 昇給ルールが曖昧
と感じたら、見直しのタイミングです。
基本給は「数字」ではなく、会社が社員に伝える「無言のメッセージ」。
そのメッセージをどう設計するかが、職場の未来を決めます。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。
状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。