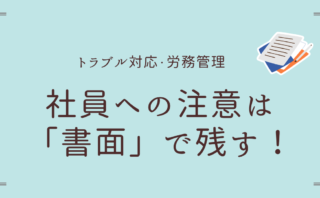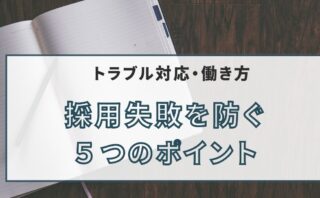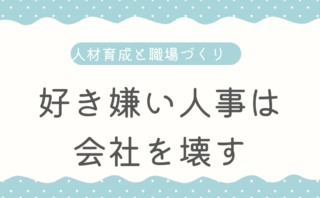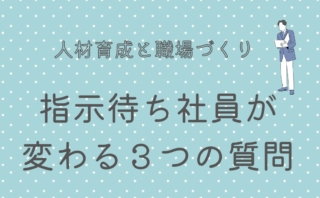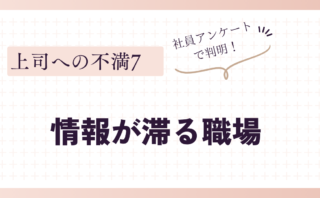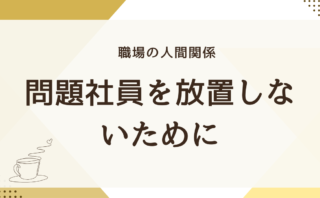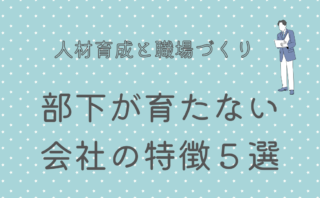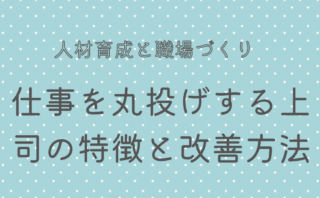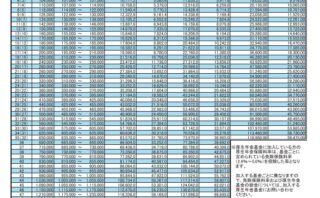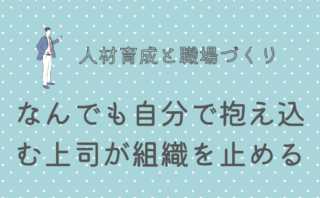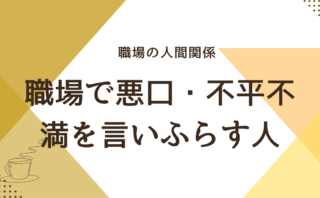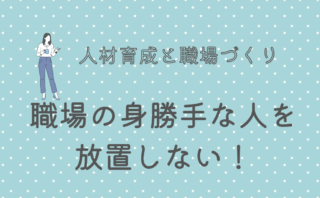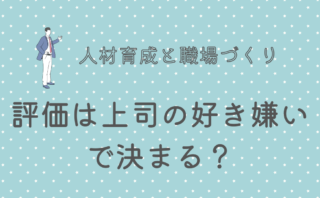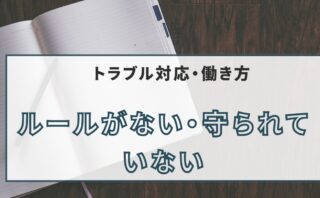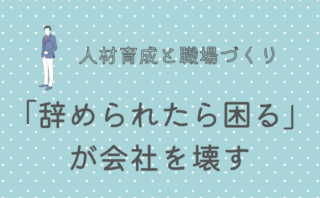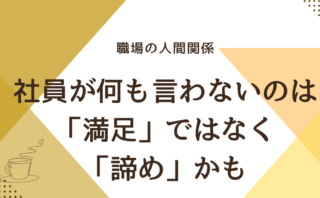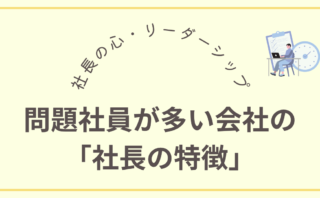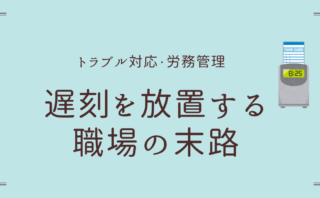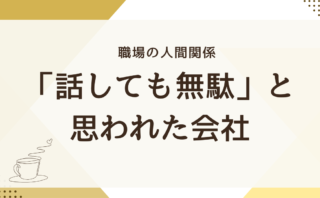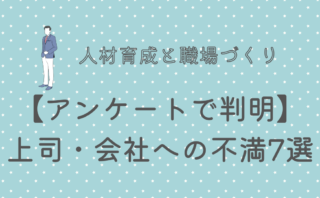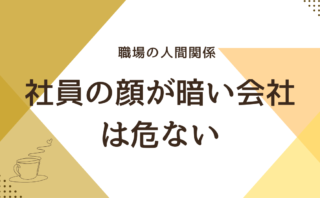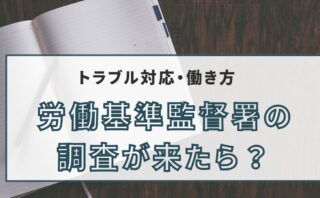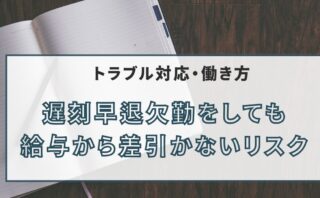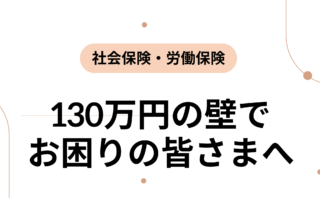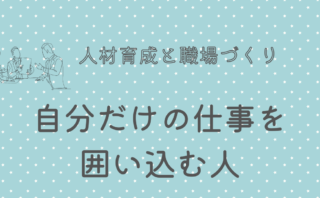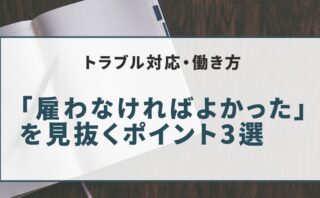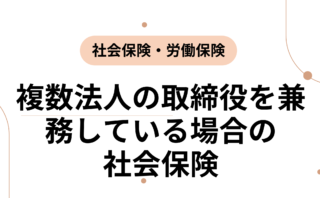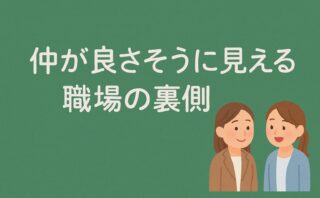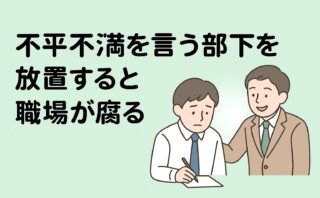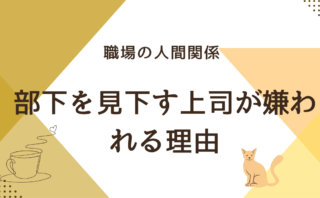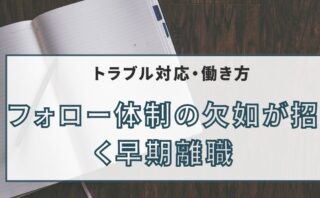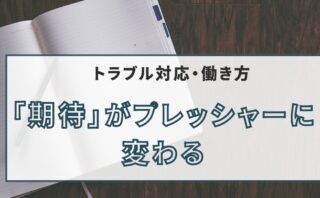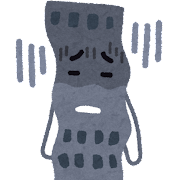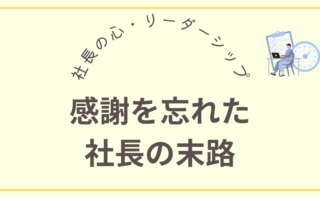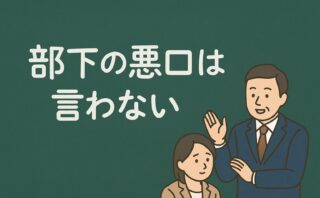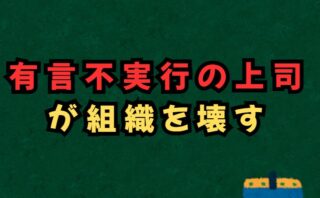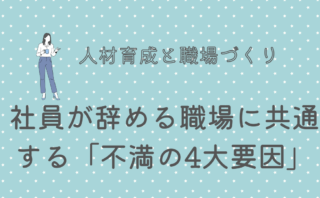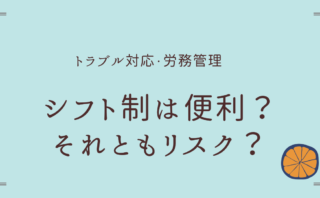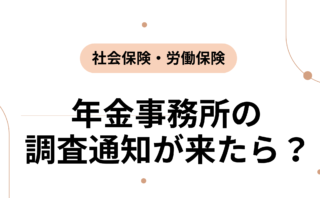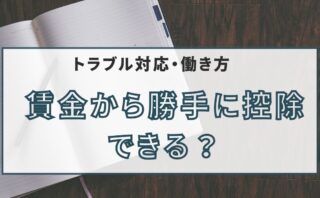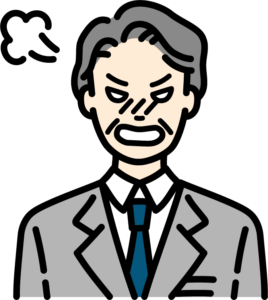はじめに
「それってパワハラです!」
近年、職場でこの言葉を耳にする機会が増えました。
令和4年4月1日からは、中小企業にもパワハラ防止措置が義務化。
つまり「知らなかった」では済まされず、会社として対策を取らなければならない時代になったのです。
では具体的に、どんな言動がパワハラに当たるのでしょうか?
厚生労働省が示す6つの典型例をわかりやすくご紹介します。
パワハラの代表的な6つの言動
- 身体的な攻撃
殴る、足蹴り、物を投げつける等、明らかに暴力にあたる行為。 これは一発でアウトです。 - 精神的な攻撃
「無能だ」「辞めてしまえ」などの暴言や、延々と続く叱責。 言葉の暴力も心に深い傷を残します。 - 仲間外し・無視
会議に呼ばない、挨拶しても返さない…。 職場で孤立させる行為は見えにくい分、長期的なダメージになります。 - 過大な要求
到底できない仕事を押し付け、「できない」と責める。 教育もせずに厳しく叱るのも同じです。 - 過小な要求
逆に「仕事を与えない」「雑用しかさせない」といったケースもパワハラ。 社員を辞めさせたい意図で行われることもあります。 - 個の侵害
プライベートに過度に立ち入る質問や干渉。 「結婚しないの?」「子どもはまだ?」なども不適切です。
詳細は厚生労働省のサイトに掲載されていますので、よろしければご覧ください。
なぜ今、パワハラ防止が重要なのか
- 従業員から労基署や弁護士に相談されるリスク
- SNSや口コミで会社の評判が落ちるリスク
- 何より職場の雰囲気が壊れ、離職が増えるリスク
パワハラ防止は「法令遵守」だけでなく、人材確保や企業イメージの維持にも直結します。
会社がすぐにできるパワハラ防止策3つ
パワハラ防止措置は法律で義務化されていますが、いきなり完璧な制度を作るのは難しいもの。
まずは今日から取り組める3つの実践策をご紹介します。
1.社内で「これはパワハラですリスト」を共有する
曖昧なままだと、上司も部下も判断に迷います。 今回ご紹介した6類型を社内資料にして、全員に周知しましょう。 「これはやってはいけない」ラインを明文化することが第一歩です。
2.相談窓口をつくる
「誰に相談していいか分からない」状態が一番危険です。 「 人事・総務に専用のメールアドレスを設ける」「 外部の社労士や弁護士を相談先に設定する」 など、安心して声をあげられる仕組みを整えましょう。
3.上司向けに“叱り方研修”を行う
叱責と指導の境界はとても曖昧です。 そこで「指導の仕方」や「伝え方」の研修を行い、部下を育てつつパワハラを防ぐスキルを身につけてもらうと効果的です。
まとめ
パワハラ防止は「大がかりな制度づくり」ではなく、
①ルールを明確にする → ②声を拾う → ③指導の仕方を学ぶ
この3つから始められます。
「会社を守る」ことはもちろん、社員が安心して働ける職場づくりにもつながります。
ぜひ、今日から取り組んでみてください。
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。
状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。