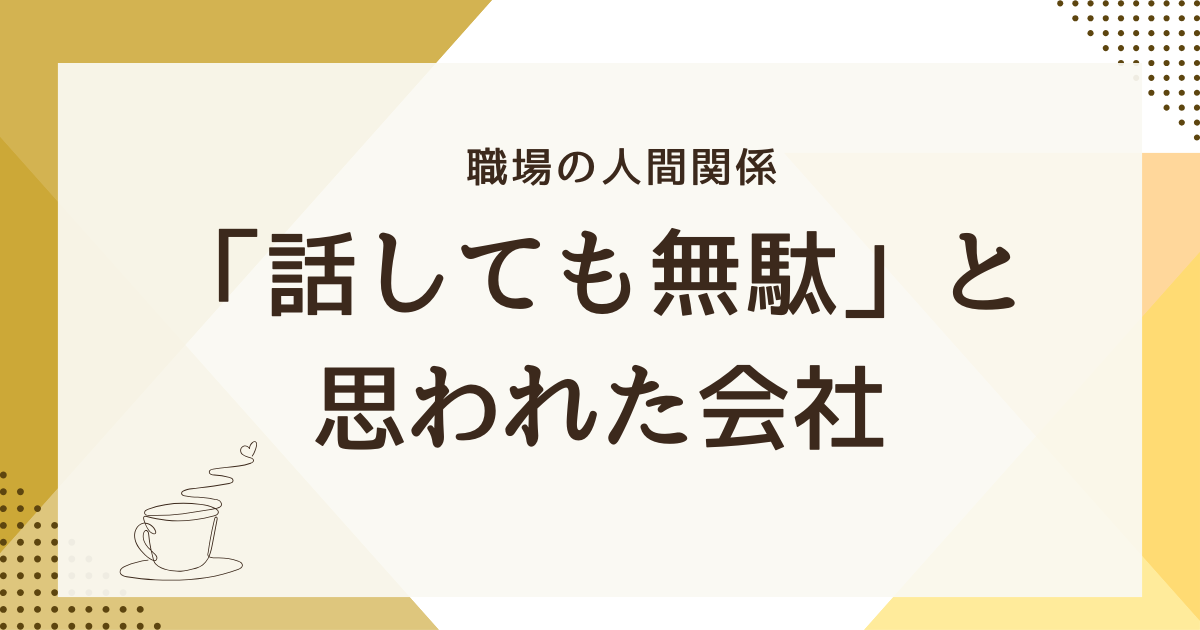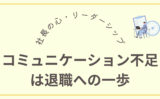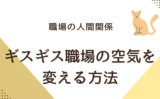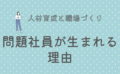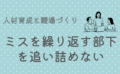はじめに:社員が黙ったとき、会社はもう危険信号
「うちの社員、何も言わなくなった」 その瞬間、会社の空気は確実に冷えています。
人は怒っているうちはまだ大丈夫。
でも、諦めて黙ったときが一番危険です。
多くの経営者は、社員が離れる原因を「給与」や「待遇」だと思っています。けれど実際は、「話しても無駄だ」と感じた瞬間、社員は会社から離れる準備を始めています。
1.「聴かない上司」がつくる沈黙の職場
会議では社長が一方的に話し、面談では上司がアドバイスばかり。
社員が話そうとしても、「いや、それは違う」「とりあえず今は我慢して」そんな言葉が返ってくる。
これが続くと、社員は話すことをやめます。
そして、表情が消え、意見が減り、最終的には静かにフェードアウトしていくのです。
2. 本音を話さなくなる3つの理由
- 否定されるから
→「でも」「どうせ」が口癖の職場では誰も本音を言わない。 - 動かないから
→意見を出しても何も変わらない。やがて諦めが定着。 - 聴いてもらえないから
→形だけの面談、形だけのアンケートでは信頼は生まれない。
3.面談は“聴くための時間”に変えよう
面談の目的は評価ではなく“対話”。「最近どう?」の一言から始めてみましょう。
- 年2回の面談を“行事”として固定
- 成果だけでなく「気持ち」にも耳を傾ける
- 雑談・ねぎらい・本音の小話を歓迎する
本音は「雑談」の中に出てきます。面談は、信頼を積み重ねる時間。社員は、聴いてもらえたと思えたときに初めて、会社のためにもう一度がんばろうと思うのです。
まとめ:「話しても無駄」と思わせた瞬間、会社は終わる
人は、叱られてもついてきます。でも、聴いてもらえない会社には残りません。
信頼とは、まず耳を傾けることから生まれる。
会社を変えたいなら、まず「聴く時間」をつくる。そこから、すべてが変わり始めます。
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。
状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。