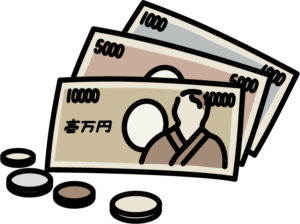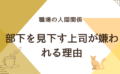はじめに
中小企業の社長や労務担当者から、「給与計算のミスが多くて困る」「担当者がすぐ辞めてしまう」といった声をよく耳にします。
実はその背景には、賃金制度へのこだわりすぎが潜んでいることが多いのです。
この記事では、複雑すぎる給与設計が招くリスクと、その解決策をわかりやすく解説します。
給与計算が複雑になる主な原因
「会社が1円も損をしたくない」という思いから、次のようなこだわり設計をしていませんか?
- 通勤手当を、月毎に最も安くなる方法(定期券or実費)で支給
(その月の出勤日数に基づき、今月は定期か普通乗車券のどっちが低いかを毎月チェックさせる) - 日によって所定時間が違う人には、会社が損をしない日に有休を取らせようとする
- 細かい設定の歩合給
その結果、給与計算が複雑になりミスが増えます。
また、給与計算担当者の負担も重くなります。
社長の“完璧主義”が担当者を追い詰める
このように給与制度が複雑なうえに、社長自身がミスを許さず完璧な再計算を求める場合、給与計算担当者は大きなプレッシャーを感じ、すぐに辞めてしまいます。
このような社長だったら、私も辞めます。
少し多めに払うぐらいが、結局トラブルは少ない
私は、給与計算は単純明快で、ちょっと多めに払ってあげるぐらいのほうがトラブルがなくていいと思っています。
労働基準監督署の立ち入り調査の際には、「この会社は、労働者に有利な計算をしているんですね」と好印象を持たれ、給与チェックがすぐに終わったケースがありました。
また、助成金を申請する場合でも、給与計算の正確性とシンプルさは大きな強みになります。
本当にこだわるべきは「賃金制度」ではなく「評価制度」
公平性や成果反映を重視したいなら、給与設計ではなく評価制度にこだわるべきです。
- 成果や貢献を正当に評価する仕組み
- 評価に応じた昇給・賞与制度
- 管理職層への評価者教育
こうした整備を通じて、社員の納得感とモチベーションを高めることが可能になります。
評価で差をつけ、支払いはシンプルに。これが、労務トラブルのない会社の鉄則です。
まとめ:給与計算は「シンプル&フェア」が最強
複雑すぎる給与制度は、ミス・担当者離脱・労務リスクを引き起こします。
「会社が損をしないための制度」が、実は会社を損なう原因になるのです。
給与制度はシンプルに設計し、成果を反映する仕組みは評価制度で整える。
この方針が、会社の信頼性・業績・社員満足度すべてを底上げしてくれます。