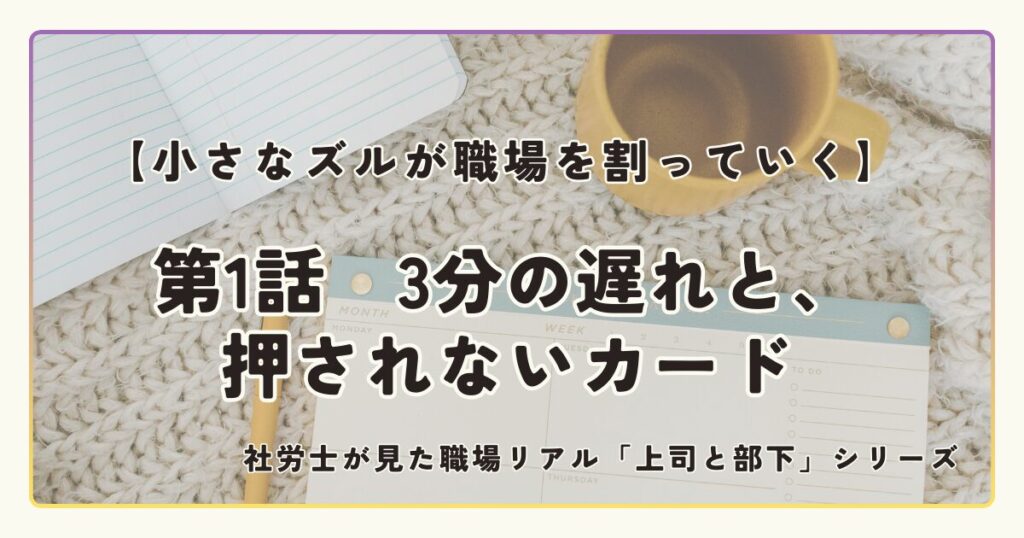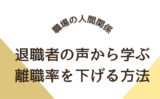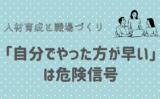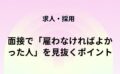1.なぜ「注意できない上司」が組織を壊すのか
問題行動を見て見ぬふりする上司がいると、職場にはこんな空気が広がります。
「あの人だけ怒られないのは不公平だ」
「言われないなら自分も適当でいいや」
「上司に相談しても無駄」
こうしてモラルは低下し、信頼関係は崩れ、組織はゆっくりと弱っていきます。
2.上司が注意できない3つの典型ケース
- 嫌われたくない
「人間関係が悪くなるのでは」と恐れてミスを放置。結果、同じ失敗が繰り返され、顧客からクレームに。 - 自分に自信がない
「自分も完璧じゃない」と後ろめたさから沈黙。若手から「頼りにならない」と見られる。 - 面倒・時間がない
忙しさを理由に後回し。やがてチーム全体に悪影響が広がる。
3.放置が招く職場リスク
- 職場のモラル低下:ルール違反が放置され、真面目な人が損をする空気に。
- 離職率上昇:理不尽さに耐えられない優秀社員が先に辞める。
- 生産性低下:小さな放置が大きな損失に発展。
具体事例
ある製造業の現場では、注意できない課長が安全ルール違反を見過ごし、結果的に労災につながりました。「誰も止めなかった」ことが会社の責任として問われ、経営層が謝罪する事態に。
4.自己診断チェックリスト ― あなたは当てはまりますか?
□ 部下のミスに気づいても、何も言わずに流すことがある
□ 「嫌われるのが怖くて」注意を控えることがある
□ 部下に反論されるのを恐れて発言を避ける
□ 忙しさを理由に、注意や指導を後回しにする
□ 注意や指摘をしづらい雰囲気がある
※3つ以上当てはまるなら、「注意できない傾向」が強いサインです。
5.経営者が取るべきサポート策
上司を責めても解決にはなりません。経営者が仕組みで支援することが大切です。
- フィードバック研修の導入
「叱る」ではなく、「気づかせる伝え方」を習得させる。 - 定期的な面談
管理職自身も安心して話せる場をつくる。部下とも向き合いやすくなる。 - 外部相談の活用
社労士やコーチなど第三者の助言で「言うべき/言わなくていい」の線引きを学ばせる。 - 登用基準の見直し
役職者には「言うべきことを言える人物」を優先して登用する。
最近は「パワハラを恐れて注意できない」傾向や、
リモート下で注意のタイミングを逃す課題も目立っています。
これらを踏まえたガイドライン整備は、経営者の重要な役割です。
まとめ:言うべきことを言える上司が会社を守る
小さな見逃しは、信頼・業績・人材を失わせる職場最大のリスクです。
しかし、言うべきことを言える上司がいれば、部下は育ち、組織は確実に強くなります。
今こそ、「伝える力」と「育てる力」 を見直すタイミングです。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士 竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
動画版
音が出ます
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。