社会保険・労働保険
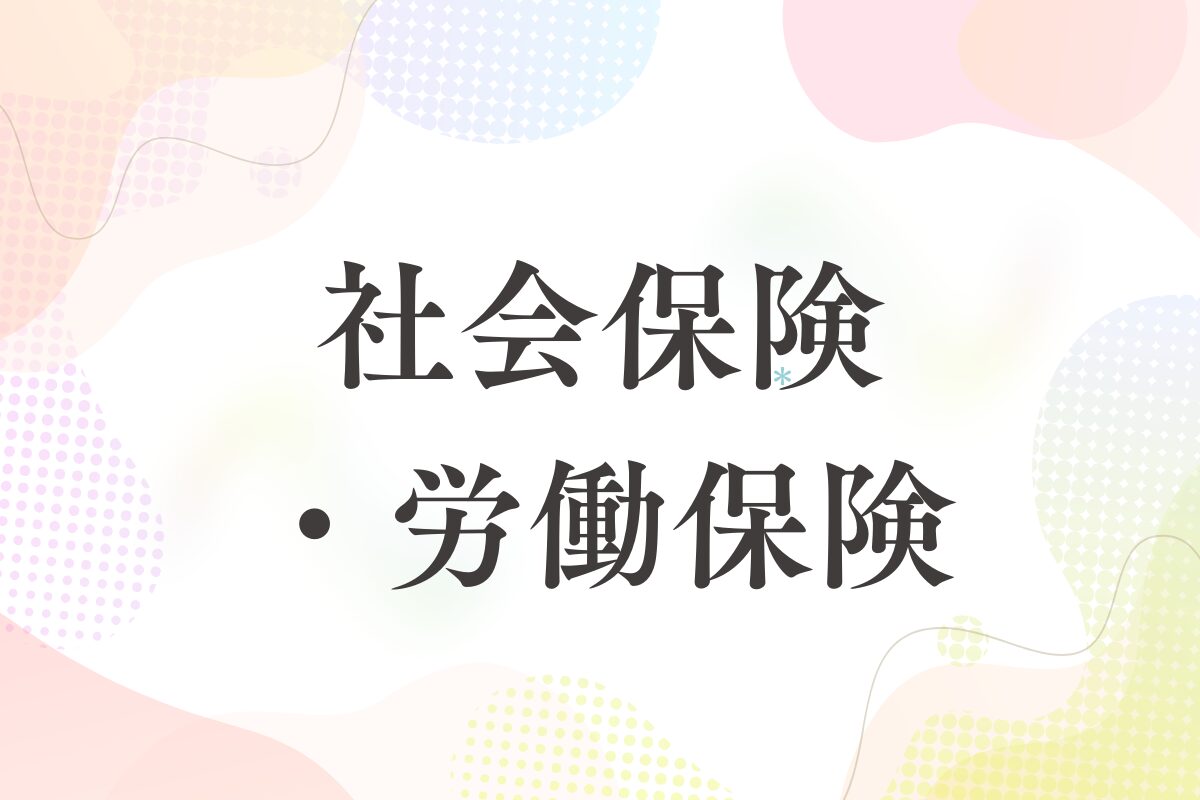
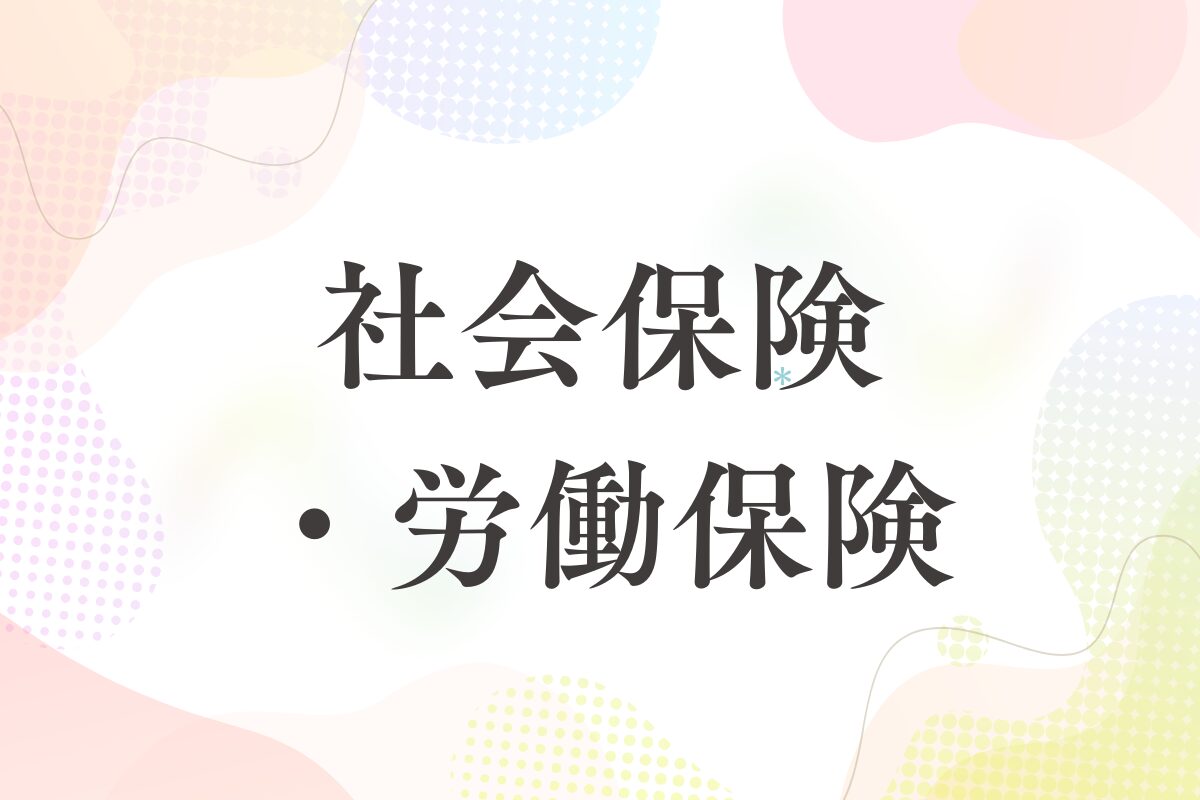
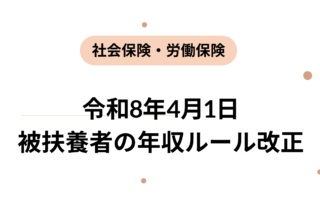 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 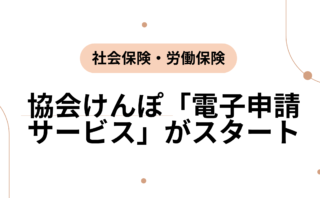 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 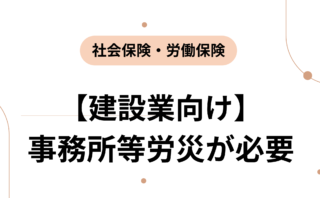 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 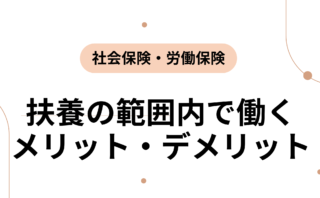 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 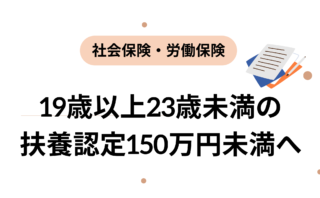 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険  社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 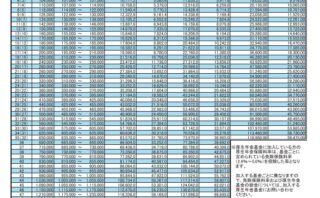 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 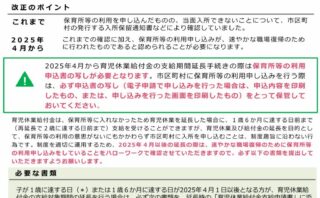 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 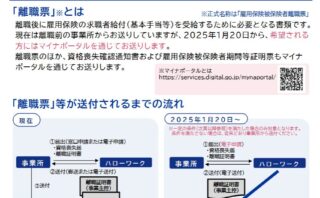 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 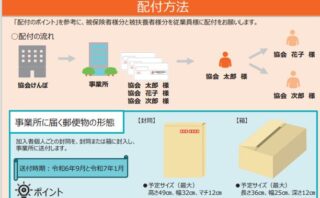 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 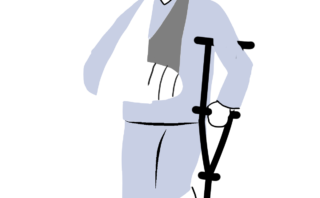 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険  社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 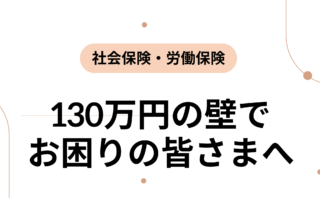 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険  社会保険・労働保険
社会保険・労働保険 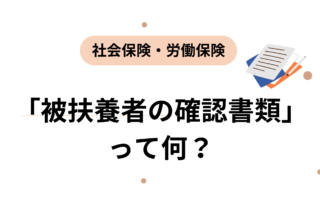 社会保険・労働保険
社会保険・労働保険