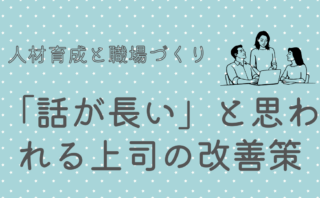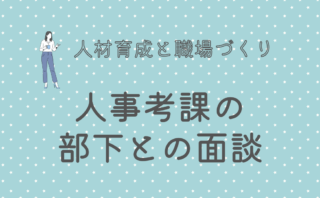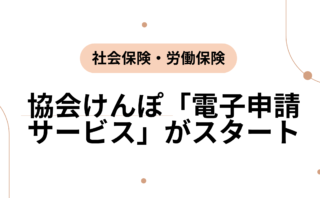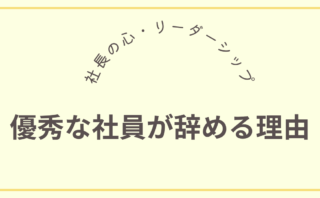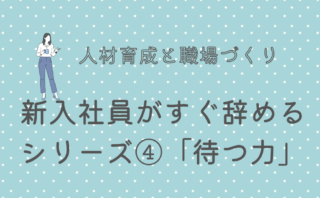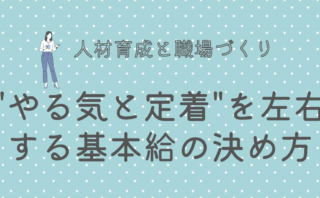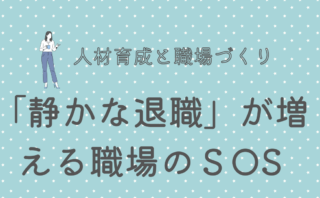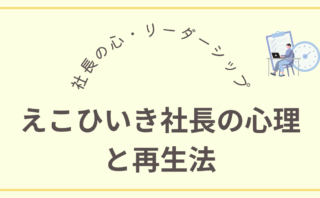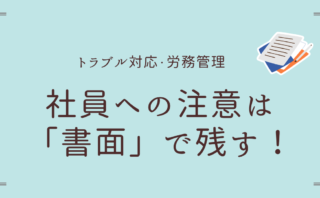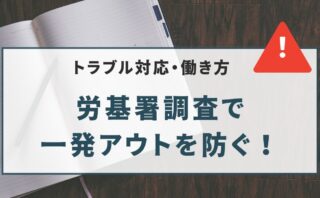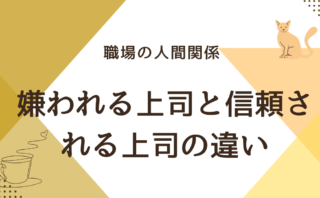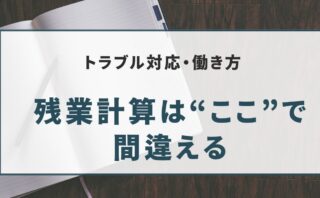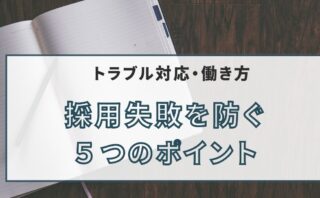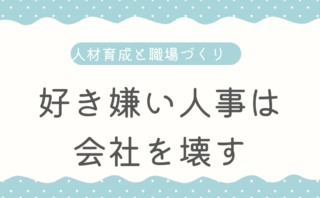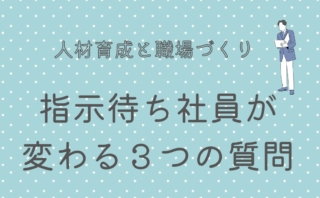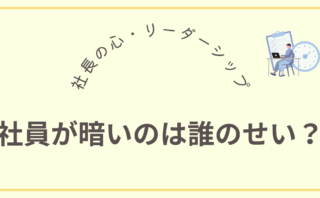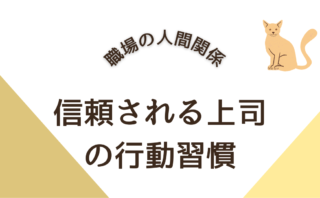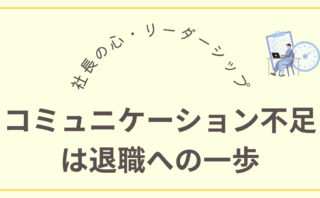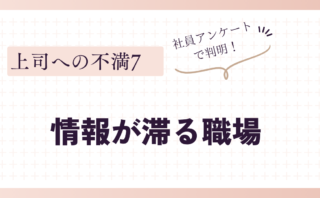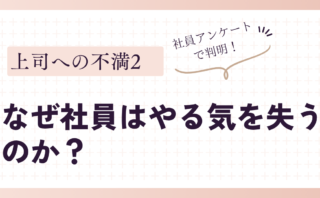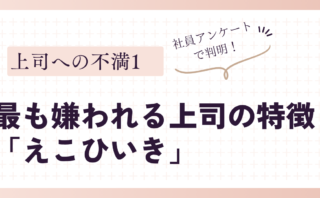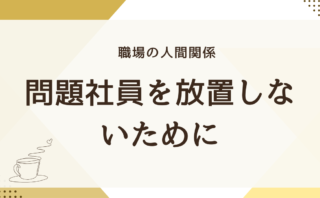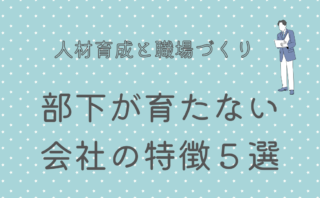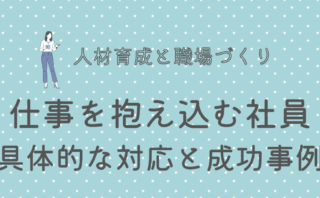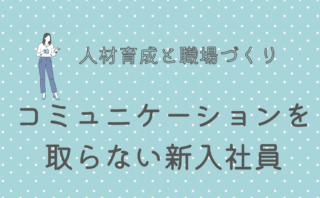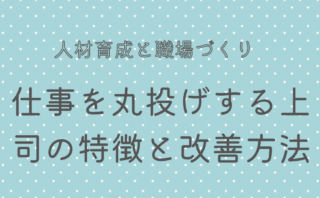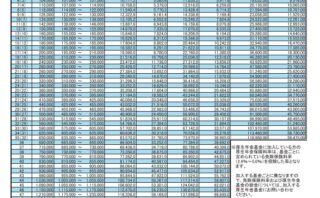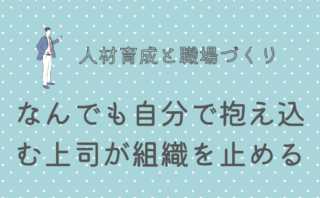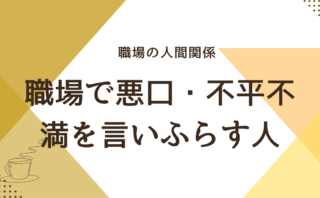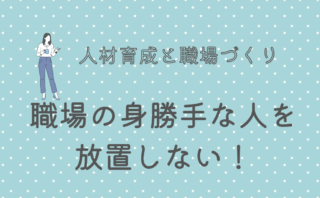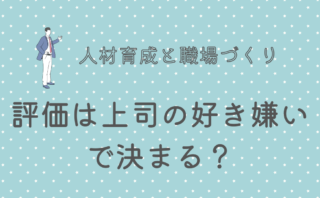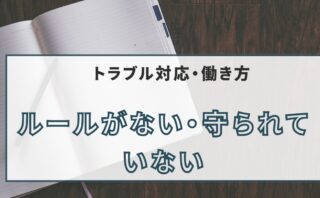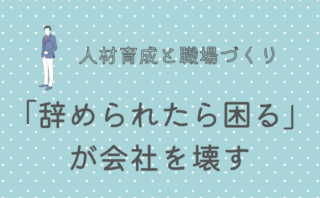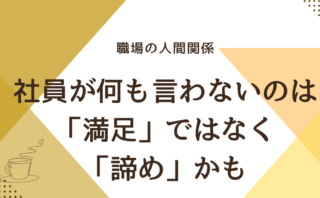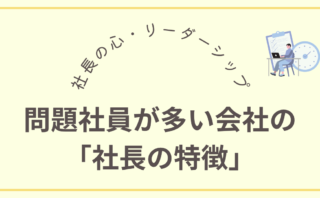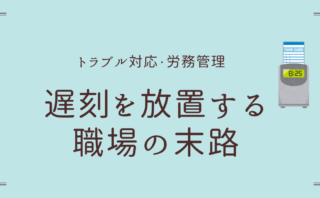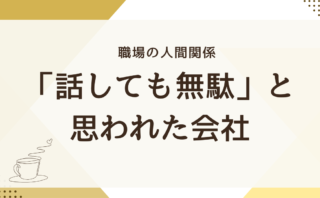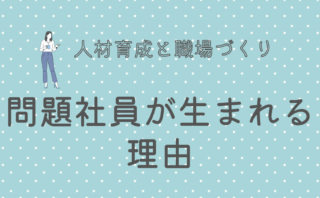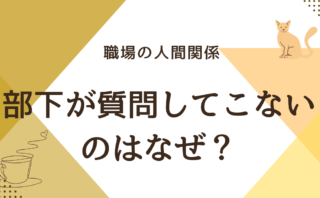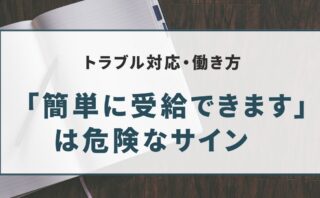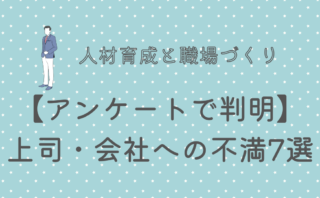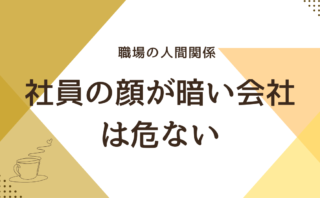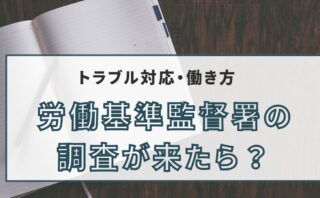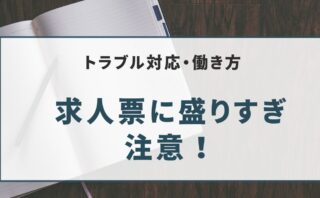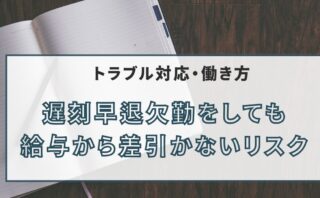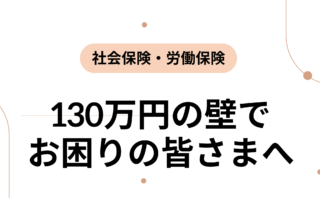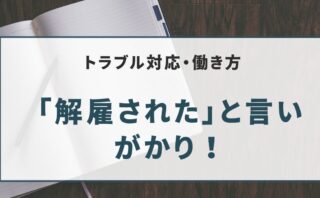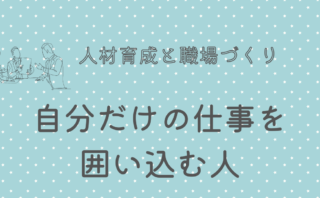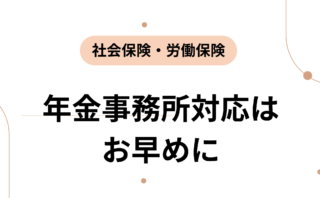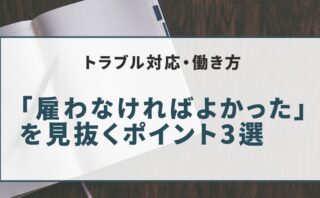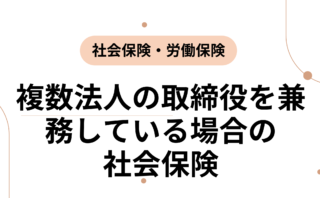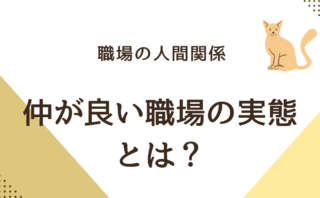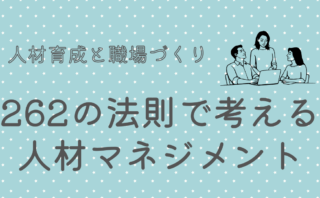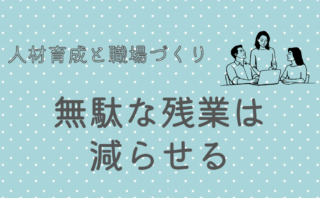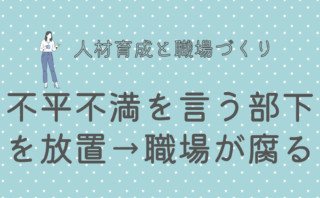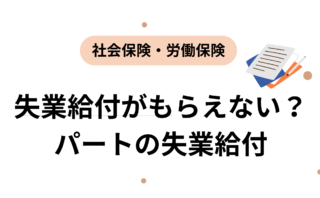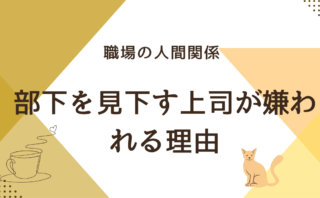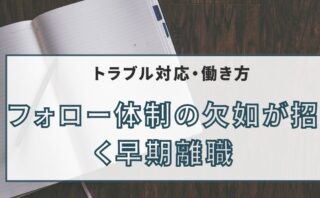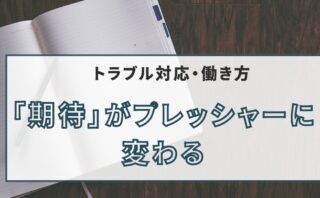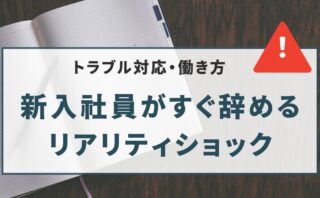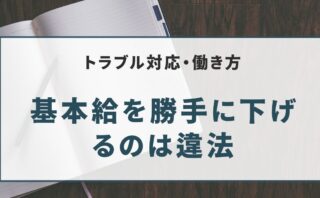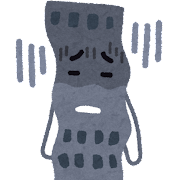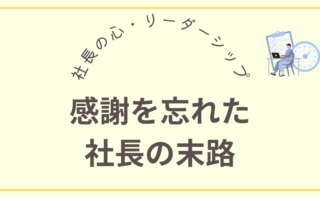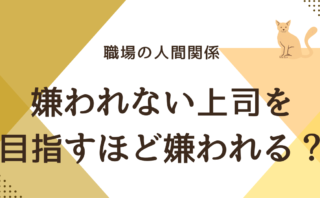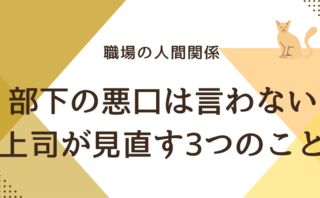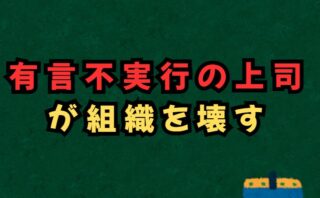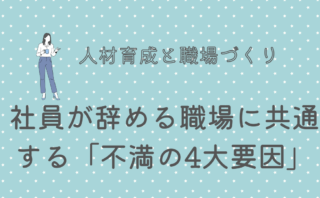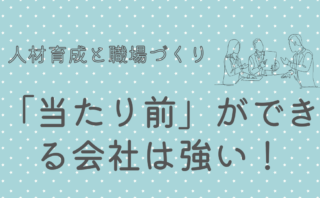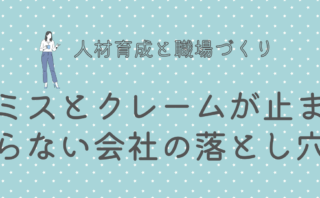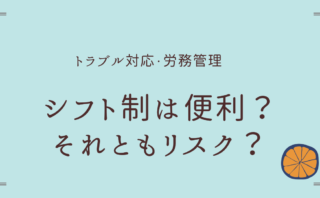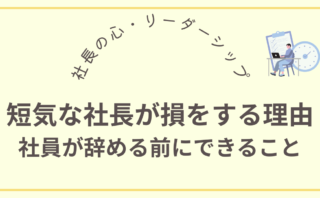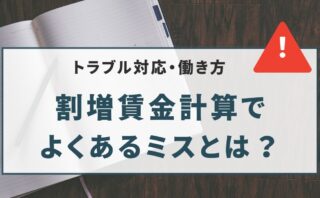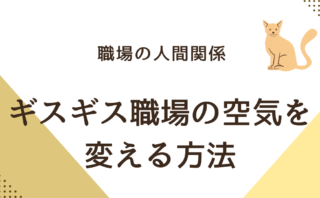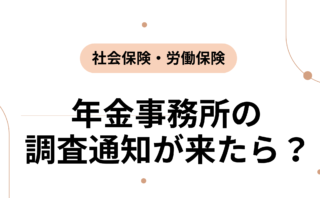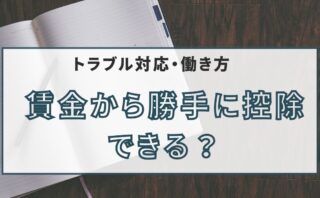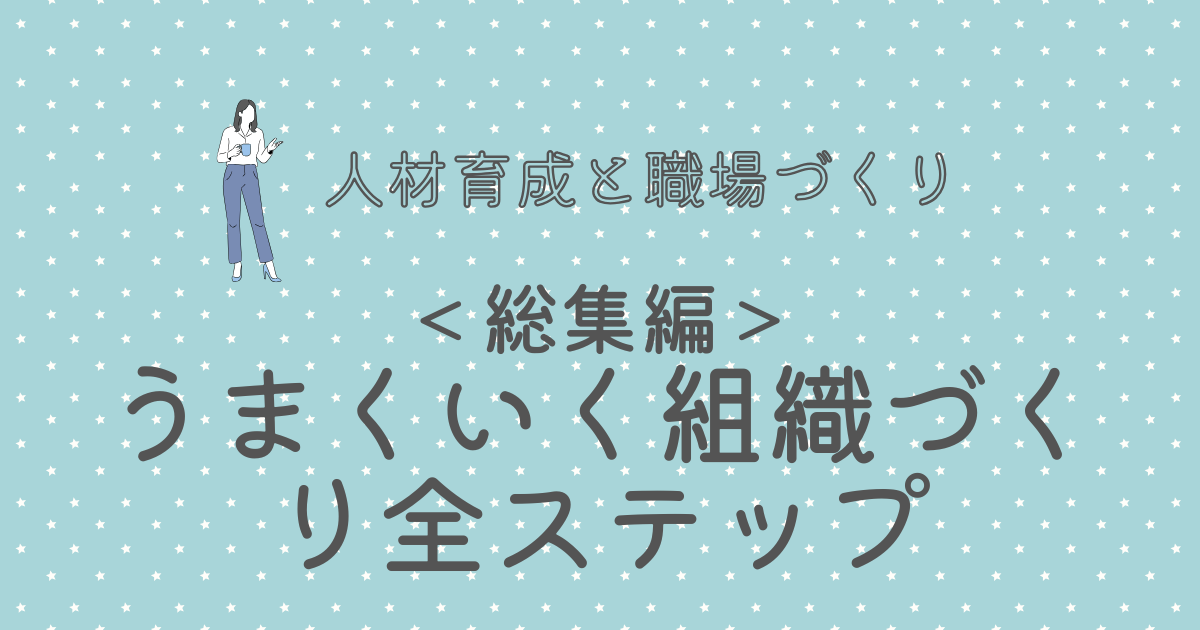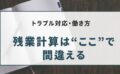―トップの覚悟から、現場の声、そして継続的な改善へ―
はじめに:中小企業の経営者や管理職の方へ
「社員が動かない」「改革が進まない」
そんな悩みを抱える中小企業は少なくありません。
この「組織づくりシリーズ」では、7回にわたって、トップの宣言から始まり、現場を巻き込み、継続的に改善を続けるまでの流れを解説してきました。
本記事ではその総集編として、各回の要点を整理します。
第1歩:トップの「宣言」から始まる
改革のスタートは、トップが 方向性・ビジョン・社員への期待 を自分の言葉で語ることです。曖昧なままでは、社員は不安を抱え、行動もバラバラに。
「まず自分が変わる」という姿勢を示すことが、信頼を得る第一歩です。
第2歩:現場の声に耳を傾ける
「自分は悪くない」と考えてしまうトップは少なくありません。しかし、現場には本音や課題が必ずあります。
- 個別ヒアリング
- 無記名アンケート
- 小グループ対話
などを通じて声を拾い、安心して話せる環境を整えること。耳の痛い意見ほど、本質を突いています。
第3歩:経営者の「度量」が試される
課題が明るみに出ると、法律違反やハラスメントといった深刻な問題が浮かぶこともあります。
ここで必要なのは、否定や言い訳ではなく、事実を受け止める度量です。
経営者自身が成長を受け入れられるかどうかが、改革の成否を分けます。
第4歩:アンケートはやって終わりが最悪
従業員アンケートはスタートにすぎません。「結果を共有しただけ」で何も改善しないで終わると、社員はこう思います。
- 「もう会社の言うことは信じない」
- 「最低限の仕事しかしない」
期待を裏切らないために、具体的な改善行動に落とし込みましょう。
第5歩:協力メンバーを選ぶ
トップの意思だけでは改革は進みません。特に管理職を中心に、現場の声を反映できるメンバーを選び、改善チームを作ります。
アンケート結果を材料に、業務の棚卸しや効率化を検討し、優先順位を決めて進める。この段階は、未来を描けるワクワクの場でもあります。
第6歩:空中分解のリスクを防ぐ
改革は紙の上ではシンプルですが、現場では感情や抵抗が壁になります。
- 習慣はすぐには変わらない
- 変化への不安や反発
- 繁忙期で手が止まる
これらで計画が停滞しがちです。
定期的にビジョンを確認し、感情の衝突を対話で解消する、この「感情マネジメント」が欠かせません。
第7歩:改善を継続する習慣を持つ
改革は一度で終わりません。
- 月1回の会議で改善報告を共有
- 成功も失敗も見える化し、当事者意識を育てる
- 三歩進んで二歩下がる覚悟で、粘り強く続ける
人の意識と行動が変わるには、最低2年はかかります。焦らず続けることが、本物の組織改革を生み出します。
シリーズを通して伝えたかったこと
- トップの覚悟
- 現場の声を聴く姿勢
- 経営者の度量
- 小さな改善を継続する習慣
組織改革は「仕組みを変えること」ではなく、仕組みを使って「人が変わること」。
だから時間がかかり、だからこそ価値があります。
まとめ
うまくいく組織づくりは、次の流れで進みます。
- トップが方向性を宣言する
- 現場の声を聴く
- 経営者自身が度量を試される
- アンケート後は改善に必ずつなげる
- 協力メンバーを選ぶ
- 空中分解を防ぐために感情をマネジメント
- 改善を継続する習慣を持つ
小さな積み重ねが、やがて「働きやすく働きがいのある組織」へとつながります。
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。
状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。