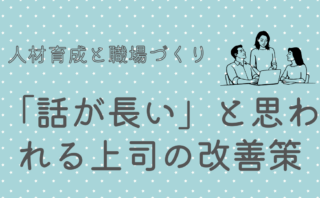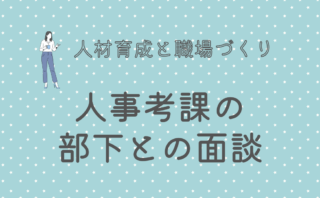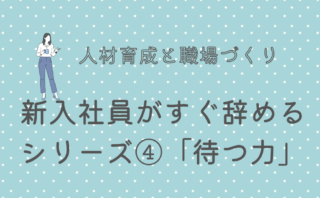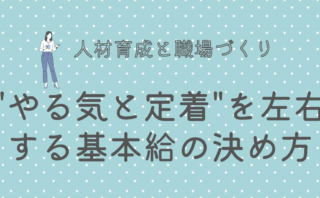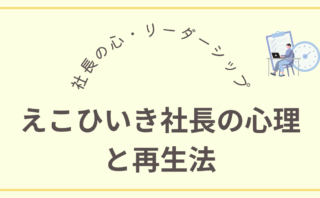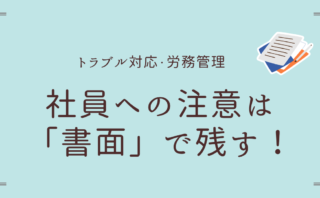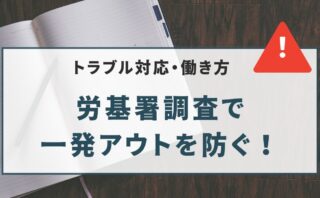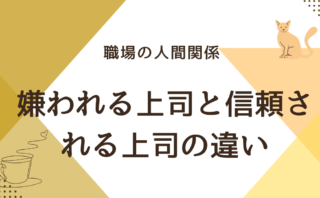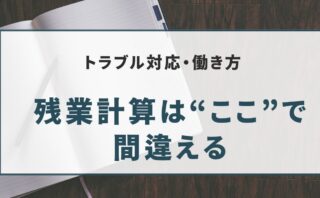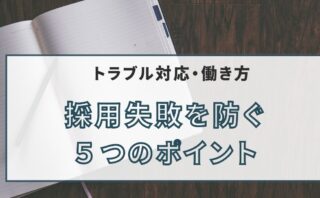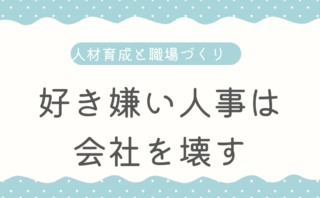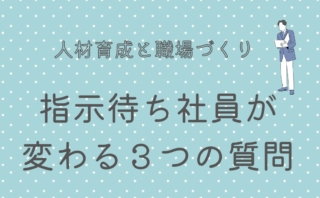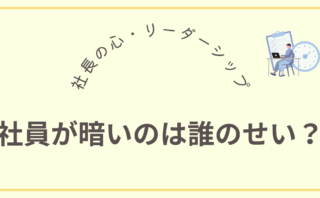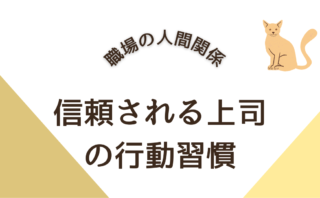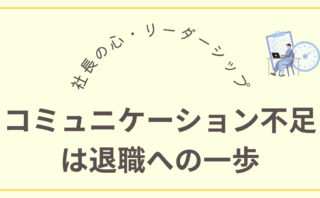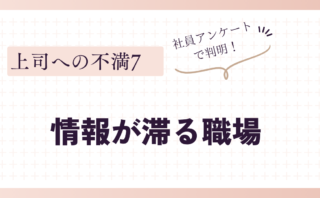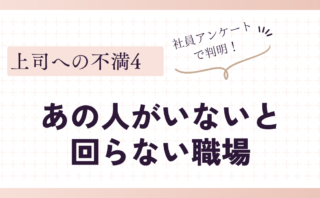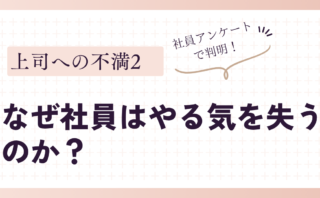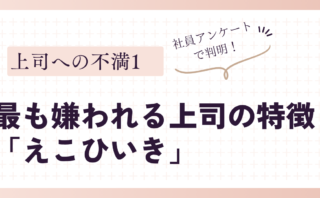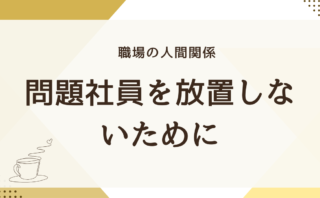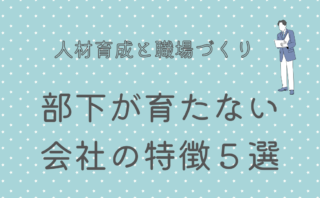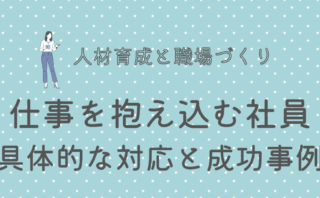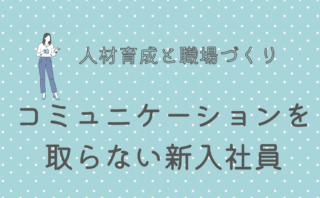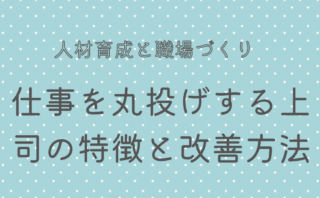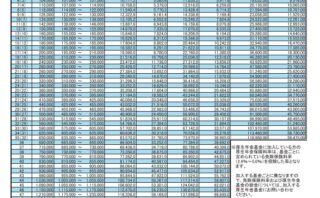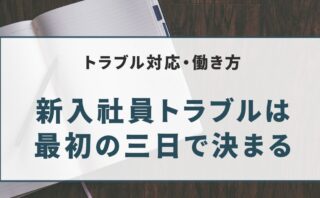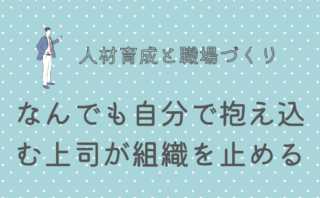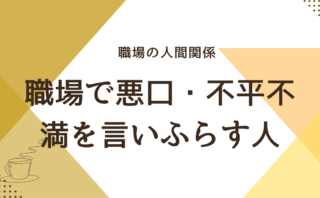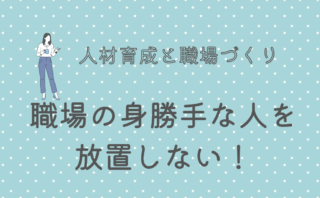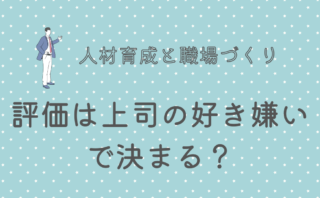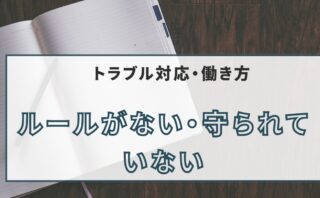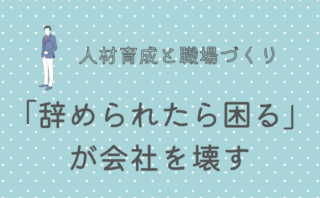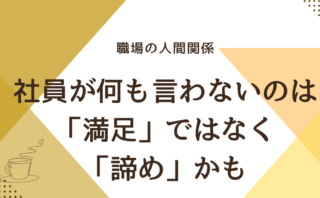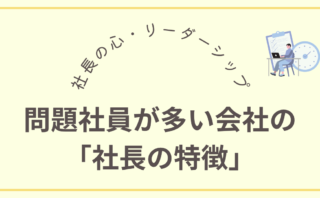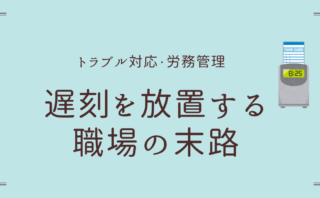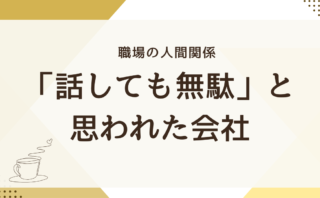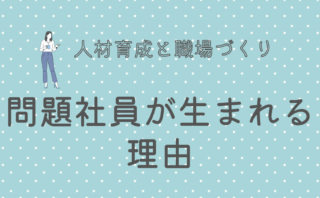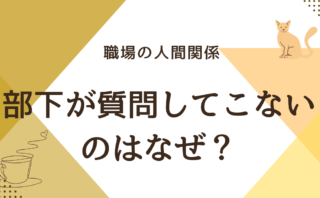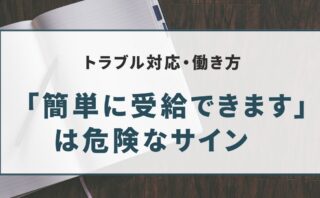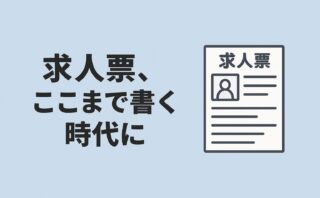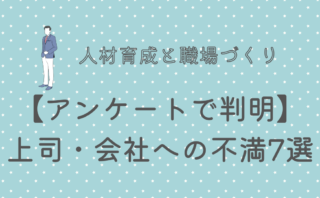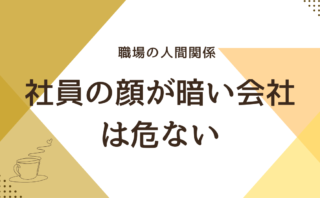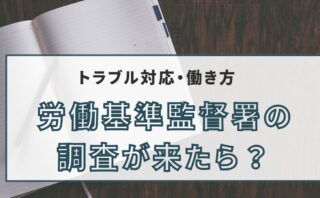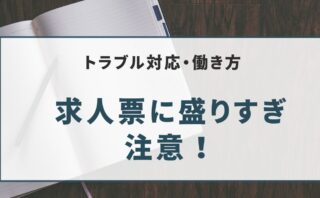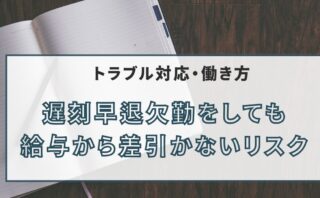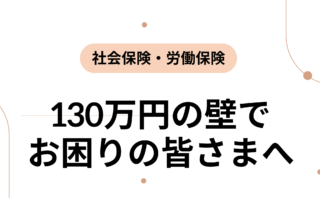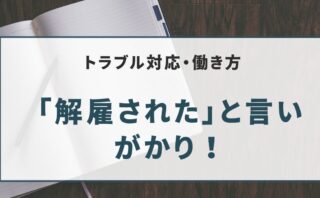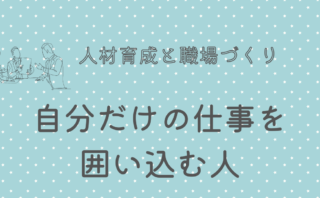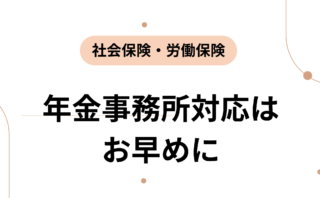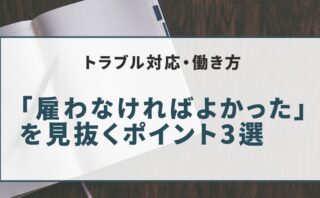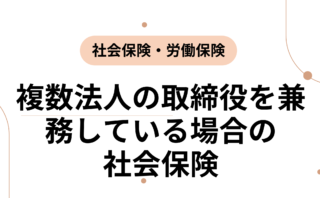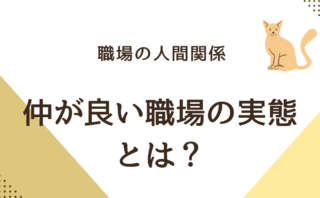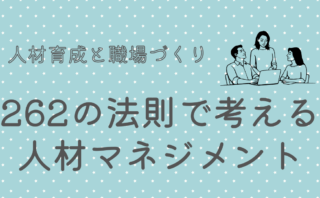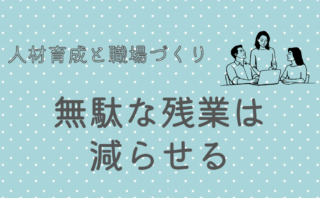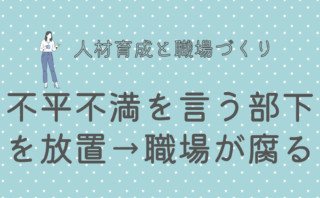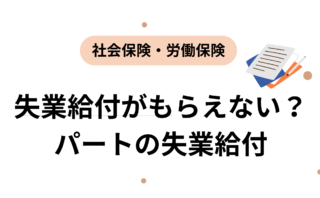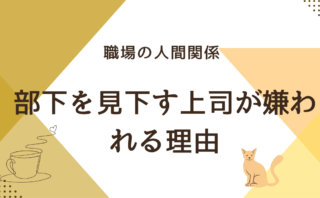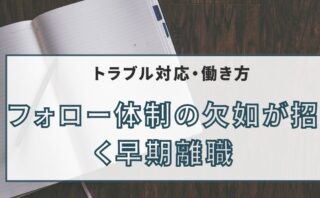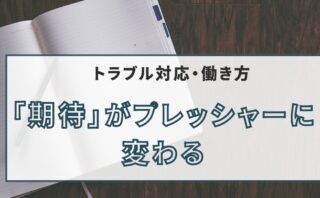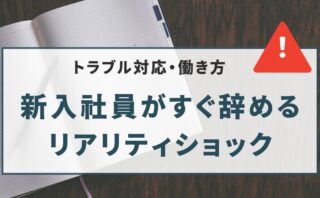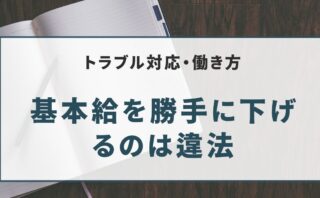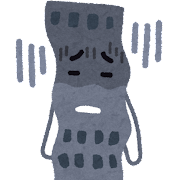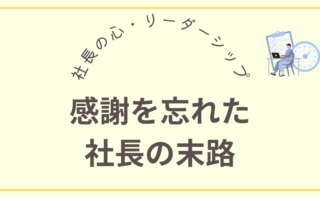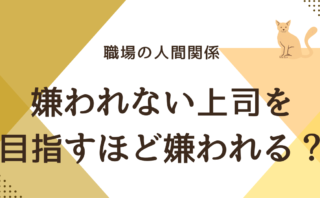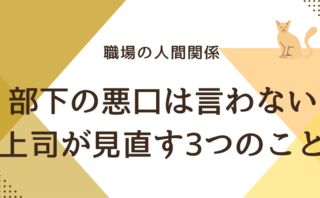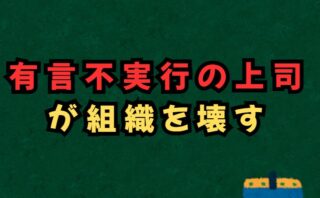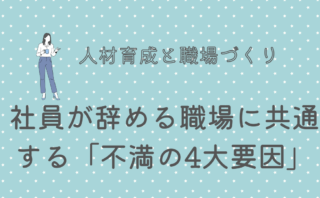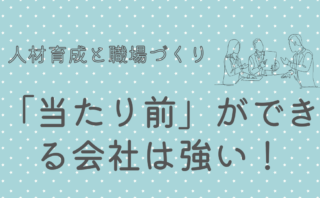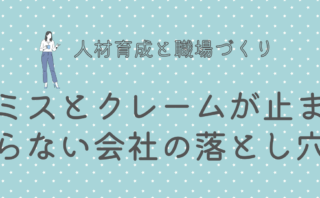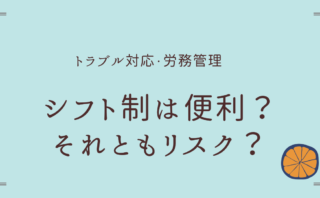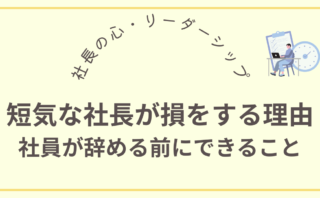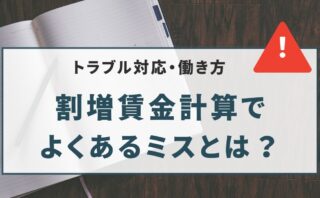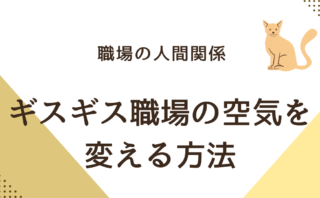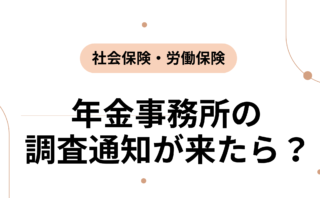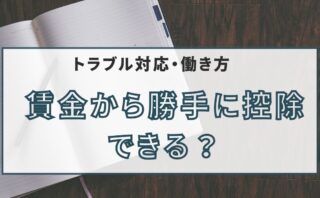はじめに
「組織づくり」シリーズもいよいよ最終回です。
今回は、組織改革を成功に導く最後のステップ=「継続的な改善活動」についてお話しします。
前回では、改革の過程で直面する「空中分解のリスク」についてご紹介しました。
そこを乗り越えた後、いよいよ本格的に改善を回していくフェーズに入ります。
ただし、ここからが本当のスタートでもあり、最大の勝負所。
「継続できる組織」かどうかで、改革の成果は大きく変わります。
課題をどんどん改善する組織へ
改善活動の内容や進め方は、組織の性質や業種、職種、規模によってさまざまです。
現場のやり方は、基本的にメンバー自身に任せます。
私の役割は、要所でのアドバイスや問いかけです。
そのための場として活用しているのが、月に1回のプロジェクト会議です。
会議では、次のようなことをレポート形式でまとめていただき、会議の場で共有します。
- 今月の改善活動とその成果
- うまくいったこと、うまくいかなかったこと
- その要因と原因の分析
- 次回の改善テーマ
- 管理職としての悩みや気づき
共有 → 見える化 → 意識改革
改善の目的は、「結果を出すこと」以上に、「プロセスを通じて意識と行動を変えること」です。
そのために大切なのが、良いことも悪いこともチームで共有することです。
共有するには、まずは課題を見える化する必要があります。
目に見えるようになると、「自分たちの問題なんだ」と気づき、当事者意識や危機感が芽生えます。
この段階から、管理職の意識やリーダーシップにも徐々に変化が現れはじめます。
改革の成果は、すぐには出ない
大切なのは、焦らず、粘り強く、継続すること。
人の意識や行動が本当に変わるには、早くても2年はかかると考えています。
途中で成果が見えづらくても、「継続は力なり」。
続けることで、組織の空気は確実に変わっていきます。
昨日よりは今日、今日よりは明日。三歩進んで二歩下がるを良しとする。
これが私の改善・育成のモットーです。
シリーズを通して伝えたかったこと
この「組織づくり」シリーズでお伝えしたかったのは、仕組みよりも人の力が組織を動かすということです。
- トップの覚悟
- 現場の声を聴く姿勢
- 継続する習慣
- 共有による信頼の構築
- 小さな改善を積み重ねる粘り強さ
組織改革とは、仕組みを変えることではなく、人が変わること。
だからこそ時間がかかり、だからこそ価値があるのです。