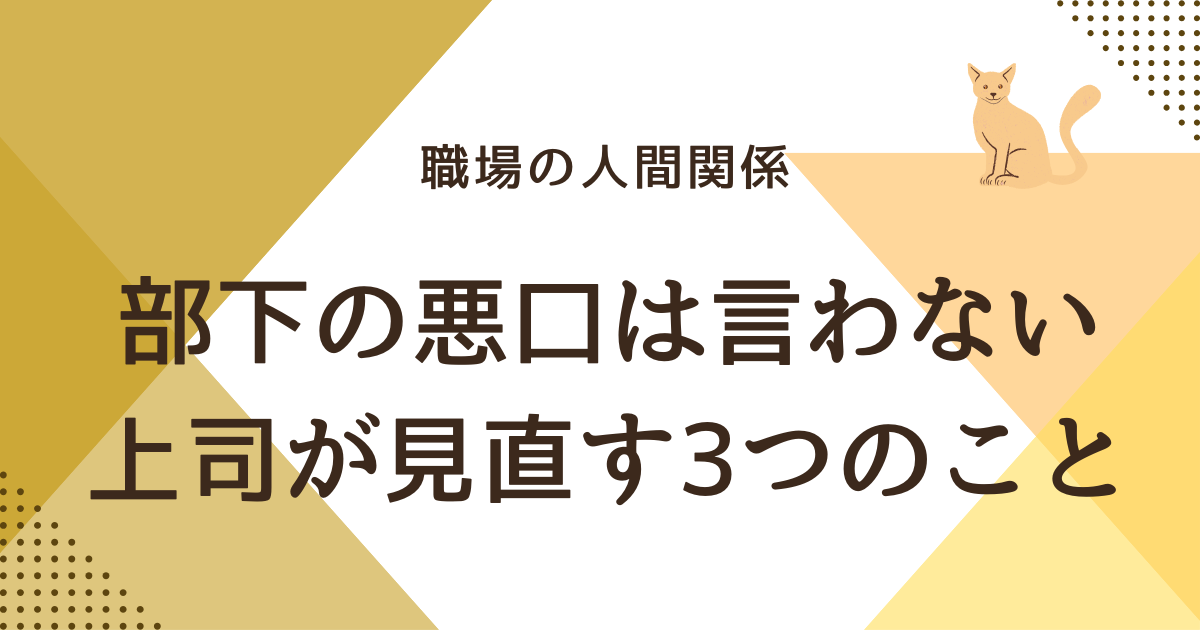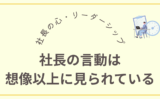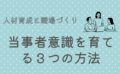はじめに
部下がミスしたとき、心の中で「またか…」と思う瞬間は、どんな上司にもあります。
しかし、その感情のまま誰かに愚痴をこぼしてしまうと、意図せず「自分の信頼」を削る結果につながります。
悪口は職場で驚くほど早く伝わり、最終的には必ず本人の耳に届きます。
すると、「部下のせいにする上司」「陰で言うタイプ」という印象だけが残り、組織の空気まで冷えてしまいます。
だからこそ必要なのは、感情の発散ではなく構造の見直しです。
今回は、悪口を言いたくなる前に立ち止まりたい3つの視点をご紹介します。
なぜ上司は部下の悪口を言ってしまうのか
上司が悪口に走る背景には、「自分のミスを認めたくない」という心理があります。
- 指示が不十分だったかもしれない。
- 期待値の共有が曖昧だったかもしれない。
でも、それを振り返るよりも「部下が悪い」とした方が簡単に感じるのです。
しかし、悪口を聞いた周囲の人はこう考えます。
- 「自分のことも言われているかもしれない」
- 「この上司は人のせいにするタイプなんだ」
こうして、上司の言葉は自分自身に返ってきます。
悪口は相手を傷つける前に 自分の信頼を失わせる“ブーメラン” になるのです。
1.悪口を言う前に、自分を点検する
部下がミスをしたときこそ、「自分の指示」を振り返るチャンスです。
自己点検リスト
□指示は具体的で測定可能だったか?
□ 期限と優先順位を明確に伝えたか?
□ 前提条件を共有していたか?
□ 途中で確認する機会を設けたか?
□ 質問しやすい雰囲気を作っていたか?
事例:
あるIT企業の課長は、新人のミスに苛立ち「あいつは理解力がない」と愚痴をこぼしていました。 しかし指示内容を見ると、専門用語ばかりで新人には意味が伝わっていなかったのです。指示をかみ砕いて伝えるようにしたところ、ミスはほぼなくなりました。
原因は「部下の能力」ではなく、「説明が難しすぎた」だけでした。
こうした自己点検の習慣が、悪口を言いたくなる場面そのものを減らします。
2.それでもイライラする時は──感情の健全な発散法
とはいえ、人間です。感情が湧くのは自然なこと。問題はどう発散するかです。
❌ やってはいけない発散法
- 他の部下に愚痴を言う → 必ず本人に伝わる
- 同僚に「あの人はダメだ」と言う → 評価者としての信頼を失う
- SNSに書く → 炎上リスク大
⭕ 健全な発散法
- 守秘義務を守れる社外の友人やメンターに相談する
- 日記やメモに書いて破る(吐き出すが残さない)
- その場を離れて10分歩く・深呼吸する
- 「怒りログ」をつける(何に怒ったか、原因は何かを記録)
→ 書くうちに「自分の指示が曖昧だった」と冷静に気づけることも
感情を「抑える」必要はありません。
大切なのは、“人にぶつけない逃がし方”を知ることです。
3.感情が整理できたら、伝え方を変える
落ち着いたら、伝え方を見直してみましょう。
| ❌ 言い方(信頼を下げる) | ⭕ 言い換え例(信頼を育てる) |
|---|---|
| 何度言えばわかるの? | この部分を改善したら、もっと良くなるね。 |
| やる気がないよね。 | どうすればやりやすくなるか、一緒に考えよう。 |
| なんでできないの? | どこでつまずいてる? サポートできることある? |
たった一言の違いで、部下の反応は大きく変わります。
❌の言葉は人格を否定し、⭕の言葉は行動の改善を促します。
悪口は諦めの言葉。
期待の言葉は成長のきっかけになります。
事例:悪口をやめた店長の小さな成功
ある飲食店の店長は、以前はよくスタッフの愚痴を口にしていました。
「Aさんは仕事が遅い」「Bさんはやる気がない」
しかし、「悪口を言っても何も変わらない」と気づき、代わりに良いところを口に出すように変えました。
「Aさん、最近笑顔が増えたね」
「Bさんの接客、すごく安定してきたよ」
すると、職場の空気が明るくなり、定着率もぐんと上がったそうです。
自分を振り返る習慣がつくと、信頼は自然と戻ってきます。
まとめ:悪口を我慢するより、構造を変える
悪口を言わない上司は、単に我慢しているのではなく、構造を変えています。
- 自分の指示を点検する
- 感情を整理する
- 伝わる言葉に変える
この3つができれば、悪口を言う必要のない職場が自然にできていきます。
「悪口をやめる」のではなく、悪口を言いたくなる状況を減らす。
その小さな変化が、信頼される上司を育てます。
動画版
音が出ます
「もしかしてうちの職場も当てはまるかも」と感じたら、早めにご相談ください。
状況を整理し、必要に応じて改善策や対応方法をご提案いたします。