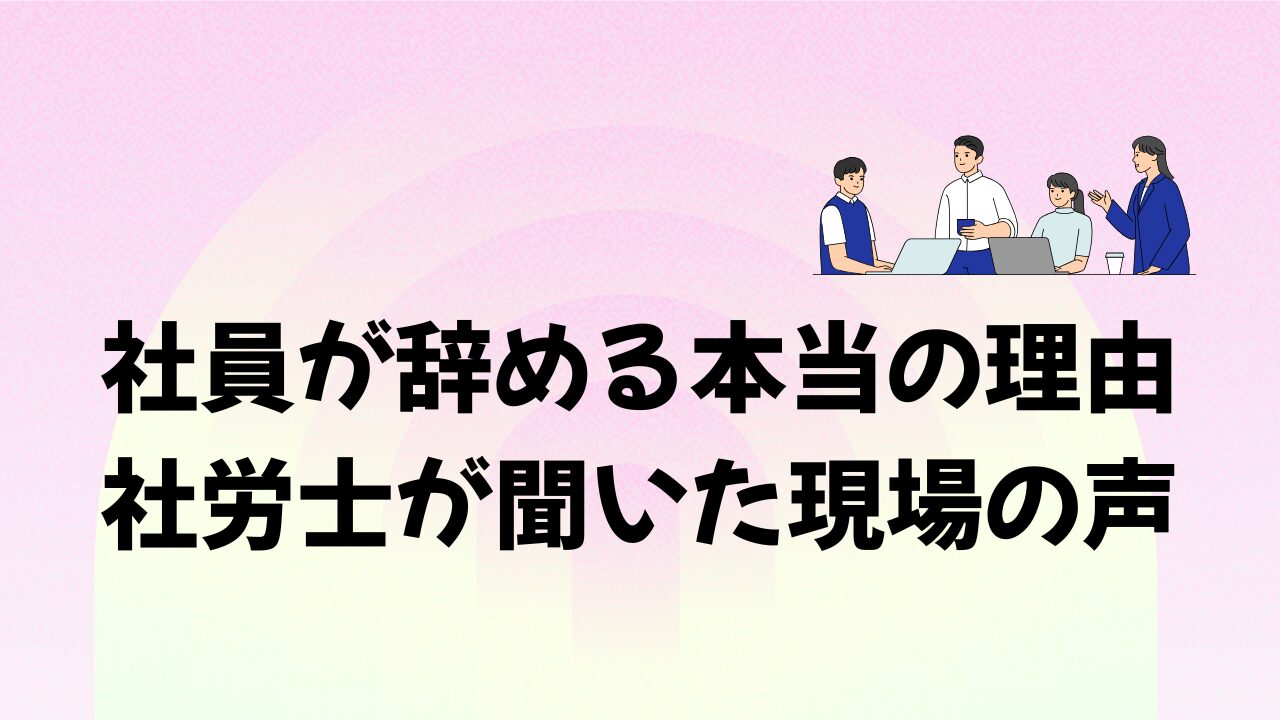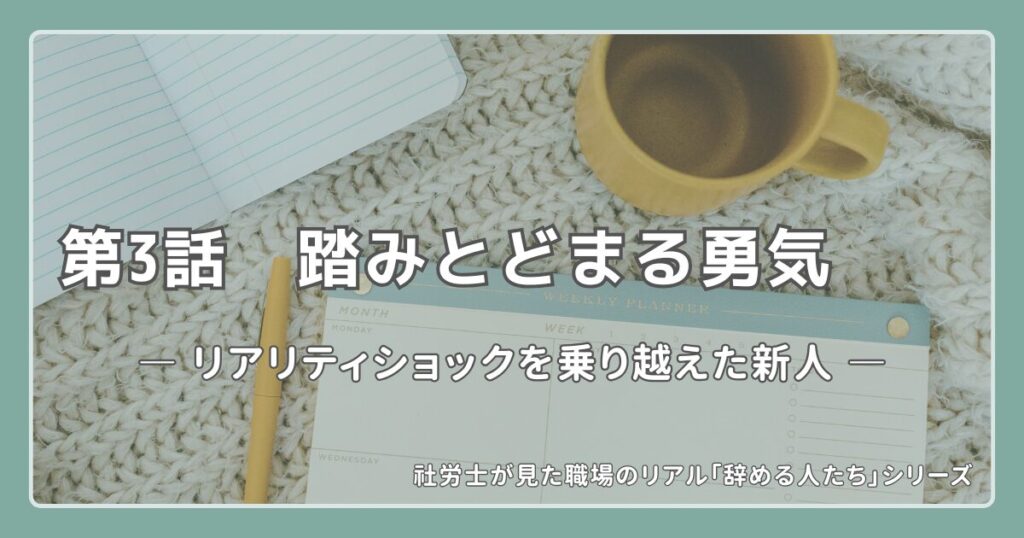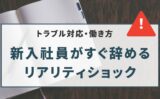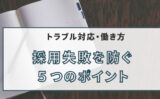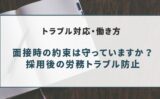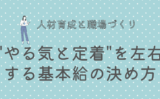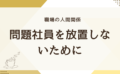はじめに:衝撃の言葉
「正直、もう社長の顔も見たくないんです」
顧問先の社員と話をしていたとき、その方はさらに強い言葉を口にしました。
ここでは書けないほどの、怒りと失望に満ちた言葉を。
社労士という仕事をしていると、経営者の耳には決して届かない「現場の生々しい悲鳴」を聴くことがよくあります。
「社長の顔を見ないだけで体調が良くなった」と語る退職者もいました。
一体、現場で何が起きているのでしょうか。
なぜ、従業員はそこまで言うのか?「最初の一歩」は小さなズレ
「クソ社長」という過激な言葉。
その原因を探っていくと、驚くほど共通した「ある問題」に突き当たります。
それは、「言っていたことと違う」という裏切りです。
- 契約のズレ:
「固定給と言われたのに、日給扱いだった」 - 責任の丸投げ:
「質問しても『誰かに聞いて』と一蹴され、フォローが全くない」 - 環境のズレ:
募集要項と実際の業務内容が、初日から大きく異なっている。
経営者からすれば「小さな違い」かもしれません。しかし、生活を預けて入社した社員にとっては、それは「この人は信頼に値しない」という決定打になります。
怒っているうちは、まだ「期待」されていた
実は、最初から社長を嫌っていた人なんて一人もいません。
むしろ、入社時は誰よりも社長のビジョンにワクワクし、会社に期待していた人たちばかりです。
- 「分かってほしい」
- 「もっとこうして欲しかった」
という思いが届かず、説明も対話もないまま放置されたとき、その大きな期待は、同じ大きさの「憎しみ」へと反転します。
本当に恐ろしいのは、悪口すら言われないこと。
期待がゼロになれば、彼らは、
- 何も言わずに去るか
- 労働基準監督署への通報や未払い賃金の請求といった、法的な紛争へと発展することになります
マネジメントスキル診断(簡潔版)
あなたの会社に「見えない不満」は溜まっていませんか?
- 労働条件(給与・休日)の変更時、書面と口頭の両方で説明している
- 社員からの質問に対し、作業を止めて相手の目を見て答えている
- 自分の非を認め、社員に「ごめん」と言えている
- 社員が「何に困っているか」を把握している
【判定】
- チェック 0〜1個:【独裁型リスク:大】
法的トラブルの予備軍です。今すぐ「正論」を捨て、対話を始めてください。 - チェック 2〜3個:【事なかれ主義リスク:中】
心の距離があります。条件の良い他社が見つかれば、社員はすぐに去るでしょう。 - チェック 4個:【共創型リーダー:良好】
社員はあなたを「パートナー」と見ています。困難も共に乗り越えられる組織です。
信頼を取り戻す「聴く」仕組み
では、どうすればこの悲劇を防げるのでしょうか。
必要なのは、高度なマネジメントスキルではなく、「誠実な説明と対話」です。
特に入社前後の労働条件の説明は、今の時代、想像以上に慎重に行う必要があります。
- 雇用契約時の「5分間の読み合わせ」:
雇用契約書を渡すとき、 「では、一緒に確認していきましょう」 と声をかけ、一つずつ読み上げます。 たった5分。 この手間が後のトラブルの8割を防ぎます。 - 「質問」を歓迎する文化:
「わからないことを聞く」ことは、最大の離職防止策です。丸投げせず、立ち止まって聴く姿勢が、安心感を生みます。 - 背景を言語化する:
資金繰りや人材不足など、経営者の事情を無理のない範囲で共有し、「なぜこの決断をしたか」を説明する努力を怠らない。
たとえ書面があっても、「言葉での丁寧な説明」がなければ、後で「話が違う」という印象を持たれてしまいます。
まとめ:敵ではなく、パートナーとして歩むために
誰だって、自分のことを悪く言われたくはありません。
しかし、その言葉の裏には「もっと信じたかった」という、かつての純粋な期待が隠れています。
社労士として私ができるのは、制度を作ることだけではありません。 経営者と従業員の間にある「ボタンの掛け違い」を直し、再び同じ方向を向くお手伝いをすることです。
「最近、社員の空気が重いな」 そう感じたら、それは会社を守るためのサインかもしれません。
手遅れになる前に、まずは社員の声をじっくり聴くことから始めてみませんか。
執筆:埼玉県熊谷市の社会保険労務士・竹内由美子(中小企業の人と職場の課題をサポート)
マネジメントスキル診断
▼職場のすれ違いを減らすために、まずはご自身のマネジメント傾向を知りましょう。
無料の10問診断で、あなたの強みや改善点をチェック。すぐに役立つアドバイスも受け取れます。
【直接相談したい方はこちら】▼▼
関連記事